ニューロリハビリテーションセミナーが再開されました!
2019年6月8日に3年ぶりにニューロリハビリテーションセミナーが再開されました.全国各地から奈良までご足労頂き有難うございました(※参加人数:300名以上).
前回のまでの当セミナーでは,「〇〇の脳内機構」や「〇〇のニューロリハビリテーション」というタイトルでセミナーを開催していましたが,休止中の3年間に『そもそも,人間の行動あるいは認知・社会性の根本的理解が必要ではないか?』という考えに至り,今回のセミナーでは“リハビリテーションのための人間理解”ということを主眼に構成しました.そのため,今回のセミナーでは,認知・運動制御・学習・社会性・身体性・発達から人間を理解することを試みました.我々にとっても,非常に挑戦的な構成にしており,どこまで参加された皆さんと共有できるか心配しておりましたが,アンケートの回答をみていると,今回のようなセミナー形式にして正解であったと実感しております.また,個別対応での質疑応答では,非常にハイレベルな質問が飛び交い,こちらも更に研究をしていかなければならないと体感しつつ,皆さんの日々の努力に感激するところでありました.今後とも,皆さんとディスカッションできることを楽しみにしておりますので,次の機会(2020年 2月22日『人間理解からリハビリテーションへ』)でも,どうぞ宜しくお願い致します.
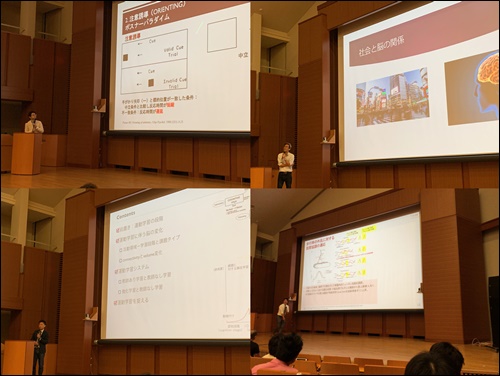
以下,講義内容と簡単な概略を記載しておきます.
「生活の基盤となる注意のメカニズム」(森岡 周)
“注意”の機能を細かく分類しながら,それぞれのメカニズムについて概説された.
「社会とつながる脳と心のメカニズム」(松尾 篤)
社会ネットワークのサイズ・共感・利己/利他的・感情などについて概説された.
「運動学習をもたらす身体メカニズム」(冷水 誠)
運動学習の種類とそれぞれの神経メカニズムについて概説された.
「自己および環境から影響される痛みのメカニズム」(前岡 浩)
痛みが心理社会的背景によって影響を受けること示したエビデンスが紹介された.
「しなやかな歩行を支えるメカニズム」(岡田洋平)
単なる平地歩行だけでなく,あらゆる環境で臨機応変に歩くことのできるメカニズムが概説された.
「身体性を形づくる感覚運動メカニズム」(大住倫弘)
身体性を形づくるのは,感覚運動の統合だけではなく,それより高次な認知的要素が必要であることが概説された.
「子どもの健やかな発達メカニズム」(信迫悟志)
自他区別・身体表象・共感・視点取得・利他性などの発達が幅広く概説された.




