第17回日本神経理学療法学会学術大会で大学院生が発表しました!
2019年9月28日,29日の二日間,パシフィコ横浜で開催された第17回日本神経理学療法学会学術大会が開催されました.
当日のオープニングセミナー,教育講演「身体性システム科学から考える「一歩先」の神経理学療法」では森岡 周先生が登壇されました.
演題発表では客員研究員の佐藤さん,博士後期課程の高村さん・藤井さん・水田さん・私(赤口)が発表を行いました.
演題名は下記の通りです.
佐藤剛介「安静時脳波を用いた頚髄損傷に対する理学療法の長期的効果の検証-しびれに着目した 1 例による予備的検討-」
高村優作「半側空間無視に対する腹側注意ネットワークへの直流電気刺激と視覚刺激の併用効果-残存する受動的注意機能の最大化を企図した新たな介入手法の試み-」
藤井慎太郎「静止立位時の重心動揺変数を用いた姿勢制御戦略の特徴分析 -神経疾患症例の特性に着目して-」
水田直道「脳卒中後症例における長下肢装具を使用した介助歩行時の非麻痺側歩幅の違いが麻痺側下肢筋活動に与える影響」
赤口 諒「慢性期脳卒中患者の把持力調節の特徴-上肢機能ならびに使用頻度との関係に着目して-」
本大会のテーマは「一歩先へ〜 One more step forward」とされ,神経理学療法領域の対象とされる神経疾患の「重複障害」に加えて,本来,理学療法士として重要なテーマである「歩行」に基づいた特別講演,教育講演等が企画されました.多数の講演,演題が重複する中でどれを聴講しようか悩まれた方も少なくなかったのではないでしょうか.私は「歩行」についての講演を重点的に聴講して参りましたが,科学の発展に伴いVRやロボットの活用する演題が多数あり,示唆に富む興味深いものがありました.その一方で,そうした最先端の技術を取り入れる上では限界点を見極め,病態,分類・評価に基づいた上での介入手段として意思決定されることが重要であると改めて強く感じました.このことから,森岡先生が教育講演で強調していた「理学療法士はエビデンスに基づいた治療を提供する専門職であると同時に,対象者にとって必要な,報酬価値のあるサービスを提供することができる専門職である」といったメッセージには,これからを担う我々若いセラピストが真摯に受け止め(概念化し),共有していくことが重要であると感じました.
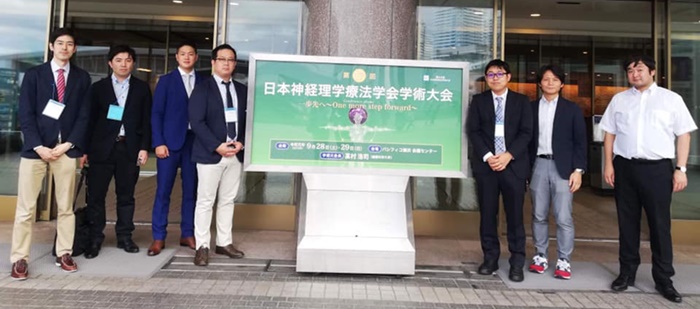
博士課程課程 赤口 諒




