第1回 畿央大学・名古屋大学 研究交流会
9月8日(日),畿央大学にて畿央大学大学院神経リハビリテーション学研究室研究交流会が開催されました.今回は名古屋大学大学院 内山研究室と記念すべき第1回の研究交流会となり,内山靖先生をはじめ大学院生,学部生の方々に遠路はるばるお越しいただきました.プログラムとしては,まず最初に,内山先生に内山研究室についてのご紹介をいただき,その後に内山研究室の大学院生から,高橋さんが「脳性麻痺児における生活の質と生物心理社会的な関連因子の探索的研究」について,川路さんが「じん肺検診受信者における身体活動量の要因に関する研究」について,佐藤さんが「Smart Walkerにおける治療・誘導刺激制御の最適化に関する実証的研究」について現在進行形の研究を発表していただきました.いずれの研究も研究背景の説明がわかりやすく丁寧に構成されており,普段聞きなれない領域の発表でしたが,初めて聞く分野の話題でも理解が深まる内容・プレゼンテーションであり,大変参考になりました.午前の最後には両研究室の数名の院生から,自己紹介も含めて簡単に研究分野や現在行っている研究の概要について発表させていただきました.午後からはまず森岡先生から森岡研究室についてのご紹介をいただき,その後,赤口さんが「慢性期脳卒中患者の把持力調節の特徴-上肢機能並びに使用頻度との関係に着目して-」について,水田さんから「脳卒中後症例における運動麻痺と歩行速度の関係性からみた歩行特性・クラスター分析に基づく特徴分析-」,西さんから「痛みの予期は目標志向的な運動制御に影響する-痛み恐怖条件付けパラダイムを用いて-」について発表していただきました.内山研究室・森岡研究室双方の院生から研究について意見交換がされ,特に休み時間に気楽な雰囲気の中で議論が自然とされていたのが非常に良い雰囲気であったと印象的に思いました.
内山研究室・森岡研究室ともに研究分野が多岐にわたっていますが,特に内山研究室では医工連携を踏まえた研究もされており,今後のリハビリテーション分野も大きく変遷していくことを実感しました.内山先生,森岡先生からもお話をいただき,両先生に共通していたことは,理学療法とは何か,どのような病態にはどのような介入をしていくべきか,ということを標準化・アルゴリズム化していくことが今我々には求められており,人間を対象としている分野なので,個別性と普遍性を踏まえた関りを高めていくことで,理学療法士の価値を高めていくことが重要であるということでした.このことを踏まえた上で,我々一人ひとりが,自分がどのような部分に貢献できるかということを考えていくことが求められているので,日々の行動を意識していきたいと再認識しました.
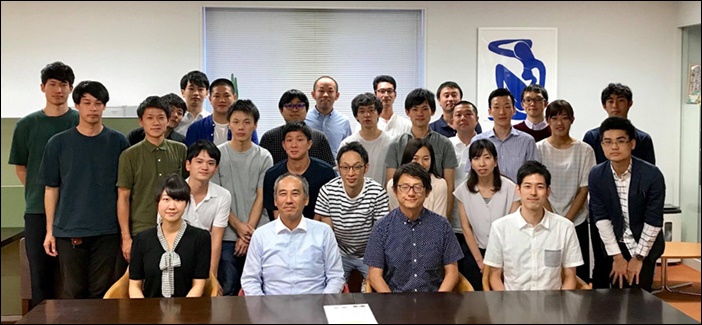
最後になりましたが,ご多忙の中快くご対応してくださり,かつ遠方までお越しいただきました内山先生ならびに内山研究室の皆様,研究交流会の運営幹事としてご尽力いただきました佐藤さんと藤井さん,そしてこのような機会を与えてくださった森岡先生に深く感謝を申し上げます.
博士後期課程 2年 重藤隼人




