第51回日本理学療法学術大会への参加報告
第51回日本理学療法学術大会に参加してきました.
今学術大会より12分科学会・5部門に分かれて行われるようになり,非常に多岐に渡る内容で全ての講演・演題を把握できませんが,私が見て・聞いたものに限り報告させて頂きます.
神経理学療法学会の「運動制御と身体認知を支える脳内身体表現の神経基盤」と題した内藤栄一先生のご講演では,腱振動錯覚の神経基盤としての反対側一次運動野と右半球前頭-頭頂ネットワークに関するお話がなされました.腱振動錯覚は,運動を行わずして,反対側一次運動野を活動させることが可能であり,運動療法が行えない麻痺や固定肢の回復に有用である可能性を指摘されました.
実際,本研究室博士課程の今井亮太さんは,この腱振動錯覚を利用した橈骨遠位端骨折術後急性疼痛に対する介入効果を調査しており,理学療法学に掲載されたその論文「橈骨遠位端骨折術後患者に対する腱振動刺激による運動錯覚が急性疼痛に与える効果 : 手術後翌日からの早期介入 」が,本学会において,最優秀論文賞として表彰されました.このような内容が,日本の理学療法界において最も権威ある学術誌で認められたことは,本学のニューロリハビリテーション研究を推し進めていくうえで,非常に大きな勇気と力になるものと感じます.

私は,小児理学療法学会と神経理学療法学会で2つの演題を発表させて頂きました.小児理学療法学会の方では,理学療法にはあまり馴染みのない模倣抑制や視点取得といった内容を含んだものでしたが,経頭蓋直流電気刺激(tDCS)を使用していることもあり,多くの方にご意見を頂くことができました.私が楽しみにしていた小児理学療法学会で行われた「教育現場と理学療法士」のシンポジウムでは,羽田空港で発生した事故の影響で,ご講演者がお一人登壇できなくなってしまいましたが,特別支援学校における支援の在り方について非常に考えさせられる時間となりました.一方で,この分野は科学的追及が困難な部分がある領域かと思われますが,私の研究分野でもあり,障害を抱えた子どもたちに価値ある研究を行わなくてはならないと思いを強くいたしました.
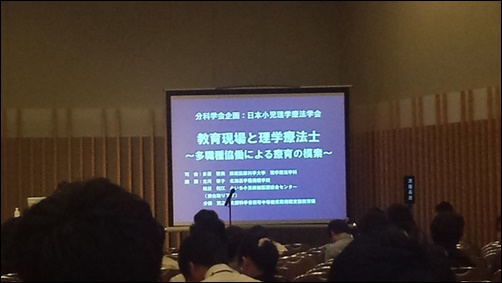
またもう一つの演題発表であった神経理学療法学会の方では,映像遅延装置システムを用いた視覚フィードバック遅延検出課題を用いた基礎研究であり,これまた理学療法にはあまり馴染みのないものでしたが,幾つかの的確な指摘を頂くこともでき,大変勉強になりました.この神経理学療法学会や日本支援工学理学療法学会では,tDCSや経頭蓋磁気刺激(TMS)などのニューロモデュレーション技術を使用した臨床研究やロボティクス技術を使用した臨床研究が数多く報告されるようになり,ニューロリハビリテーション技術は理学療法の一手段として定着しつつあるのを感じました.
私が拝聴した研究発表はいずれも高い精度で行われており,理学療法研究が非常に進歩しているのを強く感じました.その中でも,個人的に非常に面白く,今後が楽しみに感じたのは,本学の前岡浩准教授の研究報告でした.独創的で,これを臨床研究として活かすためには,どのようにしたら良いか,色々と思いを巡らされる内容でした.
その他,本研究室からは,約20演題の発表がありましたが,皆さんそれぞれ良いディスカッションができたようで,次の研究へのモチベーションが高まったようです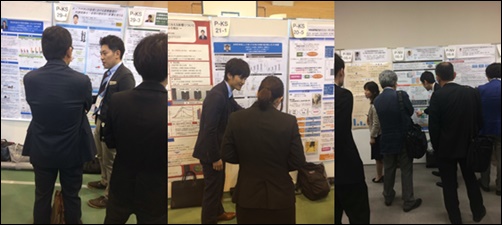
最後に本学会においても,森岡周教授の著書『リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版』が,売り上げ1位だったようです(ちなみに私も分担執筆させて頂いた阿部浩明先生編集の『高次脳機能障害に対する理学療法』は,3位だったようです).先に述べたようにこの日本理学療法学術大会においても,ニューロリハビリテーション技術に関する研究報告が非常に多くなってきましたが,その流れは森岡教授が10年前に著された第1版から始まったと考えると,敬服いたします.
畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター
信迫悟志




