第2回社会神経科学とニューロリハビリテーション研究会
2015年12月6日(日)に,第2回社会神経科学とニューロリハビリテーション研究会を開催致しました.
今回は,村井俊哉先生(京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学)教授)と平田聡先生(京都大学野生動物研究センター 教授)をお招きし,ご講演して頂きました.
村井俊哉先生からは,「「社会性」という視点から心の病気について考える」 というテーマで,社会的認知,利他的行動,共感,報酬などを取り上げてお話しして頂きました.精神科医である村井俊哉先生の視点だからこその講演は,リハビリテーションセラピストにとって重要なことを考えさせられる機会となりました.
平田聡先生には,「チンパンジーの社会的知性」というテーマで,チンパンジーの社会性などを講演して頂きました.チンパンジーの行動を根気強く観察し,それをきっかけに社会性というものを解明している姿は尊敬しました.またチンパンジー飼育での苦労エピソードを随所にお話し頂き,その試行錯誤はまさに臨床現場で苦労しているセラピストと重なる部分があると感じました.
指定演題では,松尾篤先生(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター)から「自己評価と社会性」,西勇樹先生(畿央大学大学院健康科学研究科 修士課程)から「疼痛閾値と内受容感覚の感受性および不安との関係性」を話題提供して頂きました.松尾篤先生の発表では,自分の過度な自己評価と社会的評価との関係や,内受容感覚と共感能力との関係について,西勇樹先生の発表では,内受容感覚と疼痛刺激時の自律神経活動との関係がディスカッションされました.平田聡先生にも参加して頂き,良いディスカッションも場になったかと思います.
ポスターセッションでは,15演題のポスターがあり,報酬学習・不安・抑うつ・疼痛などの社会神経科学とリハビリテーションをリンクさせるような内容が多く,時間の許す限りの活発なディスカッションだったように思います.

リハビリテーションの現場において,社会神経科学を熟知していくことは非常に重要であることは直感的に理解されてはいますが,まだまだ体系的なものではありません.そのため,まずは今回のような研究会のようなディスカッションをきっかけに継続していけたらと考えております.今後とも宜しくお願い致します.
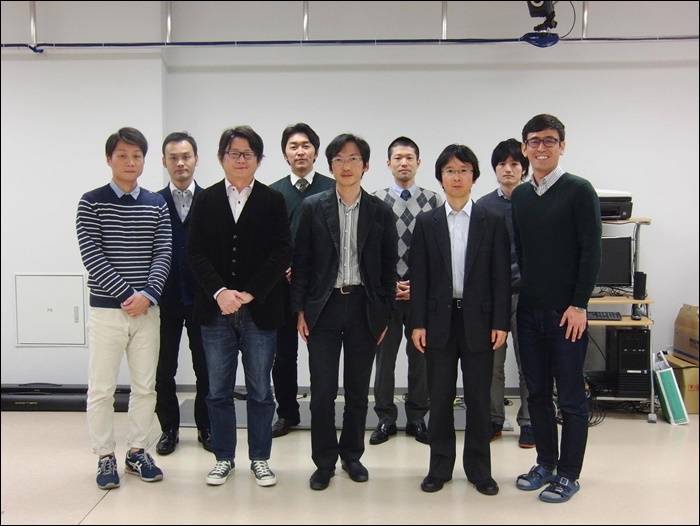
最後になりましたが,ご講演頂いた村井俊哉先生、平田聡先生に改めて感謝申し上げます.そして,ポスター発表で話題提供・ディスカッションして頂いた皆様に感謝致します.
今後とも宜しくお願い致します.




