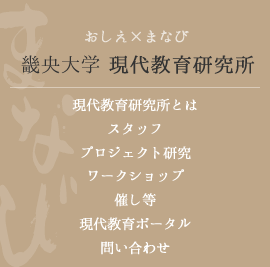2013年度プロジェクト研究中間報告会 報告
2月15日(土)に開催された本報告会は、2013年度より始動したプロジェクト研究の進捗状況を確認し、来年度に向けた研究課題を展望するというもの。4本のプロジェクトの題目と概要は以下の通り。
計画1「小学校現場における図画工作科教科書教材活用のあり方の研究」
小学校現場の状況に合わせて解釈し直し,改善を加えた図画工作科の教科書教材の実践と検証。
計画2「初等中等教育の情報化および情報科教育の実践開発研究」
初等中等教育における教育の情報化を実現する実践の開発と蓄積,教員の授業スキルの向上策の具体化。
計画3「CEAS/Sakaiを媒介とした教師、学習者、学習教材の相互関係づくりを目指した英語授業創造のための実証的研究」
英語教育の質向上のため,ICT機器の導入による教師と生徒が英語で相互に交流できる授業づくりを通した英語教育の質向上。
計画4「教員養成大学・学部における地域貢献の取り組みに関する事例研究」
日本の教員養成系大学・学部における地域連携及び貢献の取り組みの収集・比較分析と,研究所の地域貢献の可能性の検討。
白石学部長挨拶、西尾所長の開会挨拶、指導助言者の奈良女子大学杉峰名誉教授、大阪芸術大学芝村客員教授の紹介の後、各プロジェクトの報告が行われた。

計画1では、「生きる力」「確かな学力」の育成を目的とした図画工作科の学習指導のあり方が検討された。
報告では、代表の西尾正寛先生より、図工科の授業研究の枠組みが示された後、教科書題材の選択と目標設定、指導仮説に基づく学習指導案の作成から授業への反映、評価という教師の営みを捉まえた実践事例が報告された。
時間の制約の中、3事例で強調されたのは、学習過程における導入段階の工夫であった。
例えば、永井氏の題材「えらんでみよう はってみよう」では、「ざいりょうからひらめき」の教材が取り入れられた。導入段階における学習内容は「材料に親しむ」こと。それは、児童の作品イメージを膨らませるための教師の指導の意図でもあり、教材反映に向けた工夫は「幅広く発表できる材料を全員で収集し、全員で使う」というもの。
岡本氏の題材「ここにすんでいるキャラクター図鑑」では、予め教師が自校を探索し、タブレットPCにて映像を収め、導入段階の一斉学習へと反映。こうした教師の見立てが、学習者間や学習者と教師間のイメージの共有と学習コミュニケーションの促進に寄与すると仮定。山添氏の題材「表現にこめた思い」では、ゲルニカ作品を教材とし、対話を媒介に物語が膨らんでいく様子を紹介。教師の問いに対する児童の応答の質量は、とても興味深い。相互作用を前提とする研究では、法則定位よりも個性記述アプローチが相応しい場合が多い。蓄積されたこの種の質的データは、指導仮説の妥当性を検証する貴重な分析資料である。

計画2では、「教科『情報』の実践の共有と蓄積」及び「教育の情報化と情報教育に関する各学校段階での接続」を目的とした報告がなされた。
はじめに、代表の西端律子先生より、「教育の情報化」「情報教育」の概念規定がなされた。
各学校段階の接続において、双方は切り離すことができない課題であり、それは、我が国の教科「情報」の実態に浮き彫りとなっている点が示唆された。
続いて、村上氏が双方の目的に対応するべく、「情報チューズデイ」の取り組みを紹介した。
この意見交換会は、奈良県内の教諭らを対象とし、昨年度の2月に開始して以降、月1度のペースで催されている。プロジェクトの将来展望としては、この種の活動を通じて蓄積された実践例を教材集としてデータベース化するとのことである。
ところで、人間の有史以来ある現象を扱う研究は、劇的な進歩をみることは困難とされる。しかし、「情報」はこの点が大きく異なる。教育技術は、経験や研究に基づく創意工夫だけでなく、用具・道具の開発によっても進歩する。媒体の進歩は、先述した図工科や後述する英語科の教育実践にもみられるように、学習指導法の革新を担う重要な役割を果たし得る。他方、日進月歩のメディア自体の革新を背景に、研究代表が述べた「教育の情報化」の前提とも言えよう所謂「一定の授業力」という点の問題提起もまた示唆的であった。

計画3では、中学生を対象にCEAS/SakaiのE-ラーニングシステムを導入した円環型学習モデルを採用し、その効果検証を目的としている。
背景には、従来の教室型学習における相互交流学習に種々の制約があるという代表の深田將揮先生らの認識がある。
自らの思考を英語で発信できる学習者の育成を目標とする英語授業の実践研究である。実践フィールドは、古川元庸氏が勤務する中学校であり、ランディー ムース先生らも加わりサポートしている。研究計画は5フェーズで構成され、現在は第2フェーズ「授業デザインの構築」に取り組まれている。「受信型」から「発信型」という教育的意図に対応する教材の紹介では、英借文に関する言及が含まれた。
ここで発表者が課題とした英借文の規制もしくは、学習者側の利用方略の統制は、先々の効果検証を左右する。なぜなら、学習者が利用する学習方略全般に寄与しうるからである。学習者内における情報処理の深浅は、学習効果を規定する。なお、認知科学の今や古き視点を援用するなら、英語表現という行為(出力・発信)の質量レベルは、感覚刺激を入力してからの情報処理に因る。「学習」は定義上、入出力に係る情報処理過程とその変容にみる。
従来の教室型授業は表現の機会の制約から、発信用のプログラムを描く処理段階へと至る必然性を学習者にもたらしにくい。このことが学習を阻害していた可能性が考えられる。このプロジェクトを成立させているエビデンスである。発信を意図した授業デザインがどのような変容を学習者にもたらし、成果水準を左右するのかという点の検証にも期待したい。
学習指導は基本的に、学習主体と教師との関数関係で決まる。この点をいかに捉まえるかが鍵となろう。

計画4は、教員養成系大学・学部の地域貢献の現状と課題を検討し、研究所地域貢献部会による地域貢献の取り組みの可能性を探ることを目的としている。
研究メンバーは、専門分野の異なる代表の宮村裕子先生、石川裕之先生、古川恵美先生の3名。
ここでは、2013年度に実施した首都圏の2大学に関する訪問調査の結果を報告。協力機関は、早稲田大学社会連携推進室及び玉川大学教育学部である。
構造化面接他で得られた情報を整理し、作業仮説的に、地域連携・貢献の類型化が試みられた。議論の焦点は、「連携」と「貢献」を巡るもの。仮説が提示されたことの意義は大きい。地域「連携」もしくは「貢献」は、立ち位置や状況により、各々が目的(原因)にもなり、結果にもなる。地域貢献・連携において、人と人との関係づくりに視点を求めた点もまた示唆的であった。貢献や連携を“形にしていく”ための欲求や情動は、主客に関係なく、恩恵を受けるべき対象をイメージする人と人とに理想の起点があるということ。無論、主体と客体、個人と組織は互恵的な関係にあり、ここにインセンティブの課題が生じてくることがケースから伺えた。
指導助言では、杉峰・芝村両先生が各プロジェクトの講評と助言を行った。
杉峰先生は、所謂科学の分析的単純性の問題や本学のキャッチフレーズを引き合いにしながら、教科と学問における構造上の類似性や“チカラに変えるやさしさ”とは何かという点に言及。さらに、芝村先生は、ご自身の学校現場や教科分科会での経験と印象を交えながら、教科や学問の独自性と敷衍性という今日的課題に言及した。
最後に安井学科長挨拶。「相対」することの重要性にふれた上、今後の協力と労いの言葉を以て閉会となった。
現代教育学科 准教授 辰巳 智則