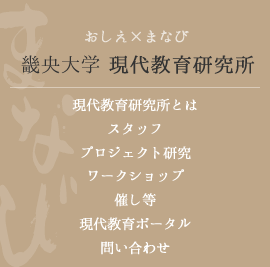畿央大学現代教育研究所 プロジェクト研究について
現代教育研究所は、平成25年度より「教師としての資質や能力を育てる」を主テーマに取り組んできましたプロジェクト研究は、第1期には4研究課題、第2期には「ポスト現代教育の在り方についての戦略的研究」を副テーマとして基礎研究2課題、実践研究2課題、第3期には、「学校の教育力向上のための戦略的研究」を副テーマに指定課題研究Ⅰ・Ⅱ、公募研究Ⅰ~Ⅳに取り組みました。
これまでの研究成果は本研究所が年度末に発刊しております「成果報告書」にて公開しており、下記リンクからもダウンロードできます。今後も年度末に研究成果を報告いたしますので、ぜひお読み下さい。
第4期プロジェクト研究テーマ
2024年度以降もこれまでの研究成果を基に学校現場に則した実践的・臨床的な研究の継続発展を目指していきます。「教師としての資質や能力を育てる」の主テーマは継続し、今期テーマとして「教師としての資質・能力を育てる~多様性を原動力とする気学校教育の探求」として取り組んでいきます。
研究の背景
少子化に伴う学校の小規模化、コロナ禍がもたらした参集型活動の制限等により、学校現場における研究活動の縮小傾向が課題になっている。また、子供たちを取り巻く環境の変化により学校が抱える課題の複雑化・困難化など、様々な変化への対応が求められる近い将来、教育に関わる人・もの・こと全てがもつ多様性を原動力とする持続可能な初等・中等教育の実現が求められよう。教育現場の今日的な課題に取り組み、本学の教育研究の活用と一層の発展を目指す。
研究内容
公募研究Ⅰ「高校生同士の対話における論理的,多元的思考構築過程の分析:主体的学びと教科横断型アプローチへの提案」
■研究代表者 現代教育学科 准教授 福島玲枝
■研究分担者 山形県立東桜学館中学校・高等学校・教諭 山口和彦、奈良県立国際高等学校・教諭 芳田亮介
2022年に施行された高等学校学習指導要領では、「多様性への対応」を重視し、論理的思考力を育てるための探究学習が強化された。これにより、生徒はディスカッションや教育ディベート活動を通じて、多様な視点を尊重し、自分の意見をわかりやすく伝える力を身につけることが求められている。しかし、論理的な議論の進め方や対話的学びの活動にはまだ課題が多く、特に英語の授業では「話す活動」の実施率自体が低い状況にある。その背景には、新しい指導法に対する教師の負担や不安があり、その解決には具体的な支援方法を示すことが重要である。
そこで本研究では、英語授業をはじめとするディスカッションやディベート活動など、生徒同士の対話に焦点を当て、会話分析(CA)によって、会話を構築し、進めるための規範を明らかにし、教師が提供すべき支援や授業運営方法を提案する。会話分析は、会話に内在する秩序や規範に基づいて発話や非言語行動を客観的に分析できる手法であり、そこから得た知見に基づき、特定の授業環境に依存せず、実践的な指導法を検討することができる。また、生徒の対話を促す授業実践に精通した客員研究員と結果を共有し、議論を重ねながら、教師の役割の再検討を行う。これにより、生徒の対話能力を向上させ、探究的で教科を超えた学びを促進する教育活動の充実を目指す。
公募研究Ⅱ 「児童が自分の見方や感じ方を広げたり、深めたりする鑑賞の題材開発」
■研究代表者 現代教育学科 教授 西尾正寛
■研究分担者 橿原市立鴨公小学校・教諭 永井麻希子、御所市立掖上小学校・教諭 岡本卓也、橿原市立鴨公小学校・教諭 金石孝弘
平成元年改訂で4学年以上の鑑賞の対象に美術作品が加えられるとともに高学年で鑑賞の指導を独立して行えることが明示され、鑑賞領域の充実が図られた。機を同じくして平成2年にアメリア・アレナスが対話型鑑賞を紹介した。指導者と鑑賞者による美術作品に関する対話を通して鑑賞者が個々に意味や価値を生成する鑑賞の方法は、美術館における研修や関係書籍、図画工作科検定教科書の題材などにより現職教員に受け入れられた(1)。平成10年改訂においては、全学年で独立して鑑賞の指導を行えること、地域の美術館などを利用することが明示され、鑑賞の充実が一層図られた。平成20年改訂では、思考力、判断力、表現力等を育む観点から言語活動の充実が全教科的に期待され、鑑賞領域では、学習の方法として、話す、聞く、話し合うなどが示された。平成29年改訂時の「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」に応じ、鑑賞の指導は対話を活動の中心とする傾向が維持されている。
学習指導要領では、鑑賞の学習で育成する資質・能力を、自分の見方や感じ方を広げたり、深めたりすることと示している。学習の方法では、材料を触ったり、もち上げたりする、表されているものと同じポーズをするなど児童の姿として示されている。言語活動にも言及しているが「低学年の児童が感じ取ったり考えたりして自然に発する言葉はそのものに自分なりの意味をもつ」(2)とし、行き過ぎた言語化の指導を避ける必要性が読み取れる。児童が見方や感じ方を豊かに働かせるためには、児童がありのままに鑑賞する姿を尊重した題材による指導が必要であり「児童の多様性を原動力にする」鑑賞の学習である。
今後、本プロジェクトでは、小学校学習指導要領の内容と教科書題材の比較検討、題材開発の視点の整理、新たな題材開発と妥当性の検討を経て、求めるべき題材の在り方の提案を目指す。
【参考資料】
(1)『みる・かんがえる・はなす』(木下哲夫翻訳,淡交社,2001)、『まなざしの共有: アメリア・アレナスの鑑賞教育に学ぶ』(上野行一監修,淡交社,2001)、『なぜ、これがアートなの?』(福のり翻訳,淡交社,1998)など翻訳されたアメリア・アレナスの著書を始め、ビデオ等も出版された。
(2)文部科学省『小学校学習指導要領解説図画工作科編』日本文教出版,p51 2017