看護医療学科 卒後教育研修「災害医療における看護師の役割」を開催しました。
2024年10月19日(土)13:30~15:00
「災害医療における看護師の役割」をテーマに、本学大学院修士課程修了生の南田哲平氏による講演会を開催しました。南田氏は奈良県立医科大学附属病院の看護師として高度救命救急センターに所属、災害支援ナースとしても活躍されています。講演会には卒業生や在学生、教員が参加、そして畿央祭に訪れた方も立ち寄ってくださいました。
災害は日本のみならず世界中のいたるところで発生しています。災害にはその発生原因から、地震や津波、台風による水害のほか、豪雪、山火事などが含まれ、被害の状況はさまざまです。そして、いつなんどき襲ってくるかわからない災害に日ごろから備えることが重要です。

講演会では、まず2011年に発生した東日本大震災の時に、岩手県石巻で救援拠点となった石巻赤十字病院の傷病者受け入れのための実際の職員の活動状況の映像を視聴しました。この映像から私たちが学ぶことがまだ沢山あることに気づかされました。
そして、南田氏の2015年のネパール地震での活動内容についてお話いただきました。国内外の災害時に派遣される看護師の活動開始までのプロセスや、発生原因が同じ地震でも発生場所によって支援活動が異なるということも教えていただきました。具体的には、国内で地震が発生した時に、広域災害救急医療情報システムの活用とともに、災害医療で最も重要な3つのTのうち、搬送(トランスポーテーション:Transportation)が陸路では難しいと判断され、航空自衛隊によって空路から行われたということや、介護を必要とする被災者の搬送にはケアマネージャーが主として活動し、そのうち医療が必要となった被災者をDMAT(災害派遣医療チーム)が搬送を担うなど明確な役割分担がなされたりしたということでした。国際的な災害支援では、たとえば2023年のトルコの大地震が発生した直後には、国際協力機構JICAの国際緊急援助隊(医療チーム)のメンバーとして看護師が派遣されたとのことでした。そのような国外の大災害で国際支援を行う国際緊急援助隊のチームは、OCHA(国連人道問題調整事務所の略。自然災害や武力紛争などの人道危機にさらされた人びとの命を救い、保護するために、国際的な人道支援活動を日々調整している(HPから抜粋))から、2022年に各国救助チームの能力を評価する国際認証の最高分類である「Heavy(ヘビー)」を改めて取得したそうです。講演を通して、実に多様な専門職が災害に備え、災害発生直後から実際に活動していることを改めて知りました。
また、被災した人々が身を寄せる避難所についてのお話もありました。避難所の設置にあたっては、日本では内閣府がまとめている避難所運営ガイドラインに沿って設置されますが、ガイドラインはスフィア基準を参考にすべきとされています。人道憲章と人道対応に関する最低基準の通称のことで、アフリカ難民の犠牲を受けて設定されたものです。避難所の汚れたトイレを使いたくないと被災者が思えば、水分摂取を控え、結果エコノミークラス症候群のような健康障害につながります。保健医療とともに、水や食糧、それ以外の物資として毛布や衣類など、また住居上でのトイレの衛生管理とゴミの処理などの基本指標について具体的に教えていただきました。当たり前のことなのかもしれませんが、日頃から大人も子供もトイレを綺麗に保つことを意識すれば、災害時もトイレの心配が少しでも減っていくのではないかと教えていただきました。また、最近では避難所のプライバシーを守るための工夫がなされていますが、避難所での簡易ベッドの使用については、高齢者のベッドからの転落に注意が必要になることもあるそうです。避難所での健康障害、ひいては災害関連死をいかに防ぐかということにも注意を払う必要があると南田氏は強調しました。
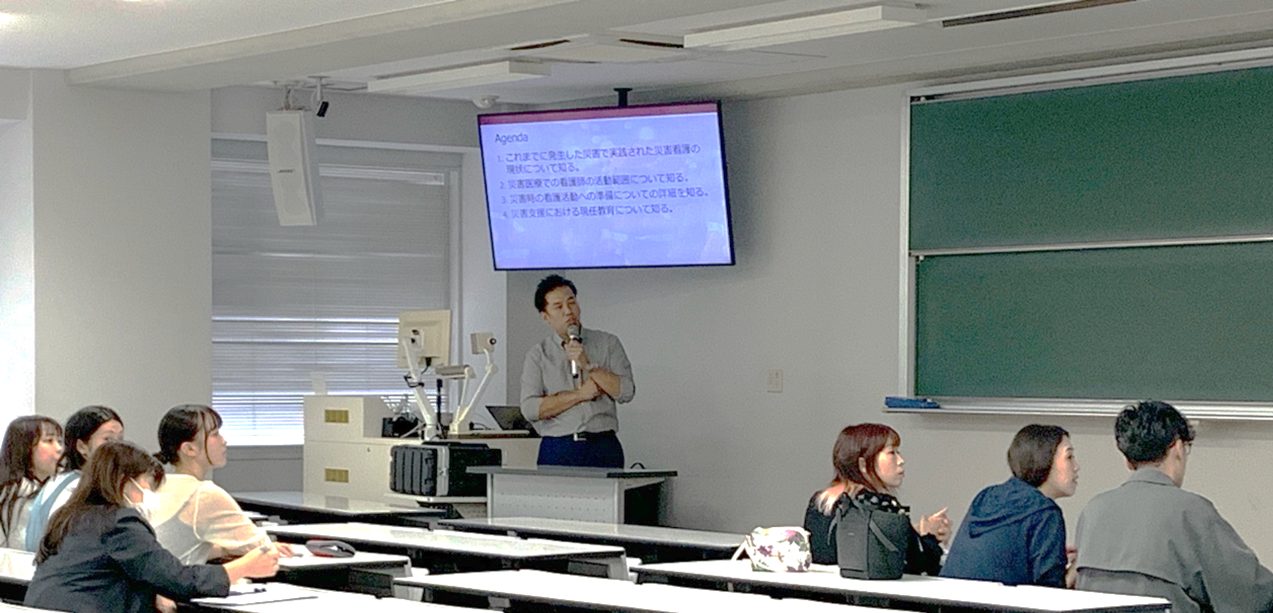
看護師として災害に備えるために必要なことは、個人としては防災計画を理解し、ロジスティックスや避難所の確認、何より地域でのコミュニケーションを心がけること、そして組織としては、災害看護を担う専門職への教育、たとえば応急処置やトリアージのシミュレーション、自身のメンタルヘルスケア、倫理的判断と法的側面の知識の獲得、グリーフディスカッションの運営などが準備として活発に行われることが大切だということです。
さらに、医療施設での看護管理において、日頃から災害への備えを意識しておくことも重要だと教えていただきました。災害が発生したその時に、たとえば手術中の患者の看護をしているとしたら、勤務中の看護師が自らの家族を心配しながら帰宅せずに傷病者に対応しているとしたら、責任者として、同僚として、先輩としてどのようにマネジメントするかを常に問うことだそうです。それを日頃から意識しておくことが大切だと南田氏は言います。
最後に、災害看護は災害が発生した時とその後だけではなく、発生前の準備段階から実践が行われており、南田氏によると災害看護を考えるとき、災害で失われてしまって、あるはずと思っているものがない場所で看護を創意工夫して行うことであり、それは看護の原点に立ち返るものであるということでした。
今一度、災害看護について考えていただけたらと思います。
