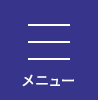|
畿央大学高校生エッセイコンテストは、本学のキーワードであり、私たち一人ひとり、そして日本の将来にとって大きな意味を持つ「健康」と「教育」について、未来を担う高校生のみなさんに考えるきっかけとなってほしいとの思いを込めて開催しています。第6回となる今回は「いのち」「子ども」「衣・食・住」「自由テーマ」の4つの分野で3698点の応募をいただきました。多数のご応募、誠にありがとうございました。審査の結果、入賞15作品と学校特別賞3校を決定しました。 |
入賞者発表
| 賞 | テーマ | タイトル | 受賞者 | 高校名 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 4 | 私たちの居場所 | 寺村 穂乃花さん | 和歌山県立耐久高等学校 |
| 優秀賞 | 1 | 背中の傷と命 | 貝沼 友希さん | 神戸市立葺合高等学校 |
| 優秀賞 | 1 | 生きる | 北村 彩乃さん | 大阪府立八尾翠翔高等学校 |
| 優秀賞 | 2 | 失敗の中から学ぶこと | 佐藤 いづみさん | 兵庫県立西宮香風高等学校 |
| 優秀賞 | 1 | 共に、闘う | 藤井 なり美さん | 岡山県・金光学園高等学校 |
| 優秀賞 | 2 | あの頃へ | 星野 葵さん | 静岡県立気賀高等学校 |
| 佳作 | 2 | 大丈夫。 | 井田 小和子さん | 京都府立加悦谷高等学校 |
| 佳作 | 4 | 今日より明日へ | 岡村 茜さん | 高知県立岡豊高等学校 |
| 佳作 | 3 | 家の心 | 川瀬 彩香さん | 静岡県立気賀高等学校 |
| 佳作 | 3 | “ここ”が好き。 | 児島 悠希さん | 愛知県立桃陵高等学校 |
| 佳作 | 1 | 「二人分」のいのち | 品川 菜穂子さん | 大阪府立千里高等学校 |
| 佳作 | 1 | 今を生きる | 中島 優香さん | 京都府立加悦谷高等学校 |
| 佳作 | 3 | 私のごちそう | 中村 奈央さん | 京都府・京都橘高等学校 |
| 佳作 | 2 | 掘りゴタツと家族 | 西田 麗華さん | 静岡県立気賀高等学校 |
| 佳作 | 1 | 人の冷たさ。人の温かさ。 | 横山 成美さん | 三重県・鈴鹿高等学校 |
学校特別賞
宮城県・古川学園高等学校 静岡県立気賀高等学校 愛知県立桃陵高等学校(1次・2次審査を通過した作品が多かった学校を選出しました)
テーマ
1いのち 2子ども 3衣・食・住 4自由テーマ最優秀賞
「私たちの居場所」
寺村 穂乃花さん(和歌山県立耐久高等学校)
家に帰らない子どもたちの映像がテレビで流れていた。なぜ帰らないのか。さまざまな理由があると思うが、多くの子どもたちは家に居場所がないのかもしれない。 私がそう考えたのは、私自身も同じような経験をしたことがあるからだ。両親からの見えないプレッシャーや、将来への不安から、親と顔を合わせるたびに口喧嘩をした。家に居ることが苦痛ですぐには帰らず、塾へ行ったり友達の家へ行ったりしていた。 そんなとき、私の居場所になったのは学校だった。担任のT先生は、ことばにしにくい気持ちを急かすことなく隣でずっと聞いてくれた。同じような悩みや感情を抱える友人もたくさんいた。共感し合うことで、私は安心と自信を得たように思う。その中に、Kという友人がいた。彼女は母親から虐待をうけていた。その左腕には自らの手で傷つけた傷がいくつもあり、祖母に引き取られたのだが、自傷行為はそのまま続いていた。私にはその傷が、彼女が負った心の傷の深さを表しているように思えた。T先生は担任となってすぐ、Kの自傷行為に気づき、Kを抱きしめ、心の傷と向き合った。私たちは先生とともに心の中を吐露し合い、自分たちの気づきを増やしていった。半年が過ぎる頃には、Kの自傷行為はなくなっていた。私たちにとって、その時間こそ、自分たちの存在を確認できるときであり、自立への一歩を踏み出すステップであったと考える。そういう居場所としての学校が、私たちには必要だったのだ。 そんな経験を通して、私は教師になりたいと考えるようになった。あのときの私やKのように、一人で孤独を抱えている子どもがきっとたくさんいる。孤独を望んでいる子どもなんて一人もいない。私はT先生のように、子どもたちの見えないSOSにいち早く気づき、心の傷に寄り添える教師になり、学校を安心できる居場所にしたいと考えている。【作品講評】
「居場所がない」という言葉は、一見すると、空間的な意味を指し示す軽いひびきをもつ言葉のように思われるが、今では、人間としての存在を揺るがすような状況、あるいは深刻な心の悩みを表す言葉として用いられることが多い。だからその言葉が発せられたとき、あるいは自覚されたときには本人の、ときには生命を危うくする警告のサインが出されているものとして受けとめなければならない。「私の居場所」と題する本エッセイはそうした「居場所」という言葉のもつ意味の重大さや「居場所づくり」の重要性を3人の人物の関わりをとおして簡潔に語っている。 家庭に「居場所」を見出せず自分を見失いがちだった「私」が見つけた「居場所」は、「学校」だった。担任のT先生、そして親から虐待を受けて自傷行為を繰り返し生命の危機さえあった友人Kとの心の触れ合いを語る箇所は、愛情と信頼が人間の立ち直りにどんなに大切かをあらためて思い起こさせる。そうした触れ合いをとおして筆者は、「居場所」としての学校に期待を寄せ、将来は、T先生のような教師になりたいと考える。 安心して過ごせる「居場所」があるということが子どもたちにとってどんなに大事か、また、学校を子どもたちの「居場所」にする努力をしようではないか、本エッセイは、読者にそんな思いをいだかせる含蓄のある作品となっている。 畿央大学教育学部長 白石 裕優秀賞
「背中の傷と命」
貝沼 友希さん(神戸市立葺合高等学校)
小学校五年生の冬、私は生まれて初めて自分のもつ「いのち」を感じた。 動脈管開存症、それが私の病気だった。心臓病ではあるが、手術すればほぼ確実に治る病で、手術の成功率も100%に極めて近い比較的簡単なものだ。 先生は病気について、手術について、小五の私にも分かるように丁寧に教えてくれた。私も、手術をすれば治るのだと何の疑いもなく信じていたし、大丈夫?と聞かれ、元気に「うん!」と答えたことも覚えている。 でも、手術の前々日に入院して、病室のベッドで夜を迎えた時、私は初めて恐怖を感じた。無機質なベッドや、カーテンや、天井が、私に「生」を感じさせなかった。怖くて怖くて、たまらずナースコールを押した。用事なんてなかったけど、誰かに会いたかった。結局、のどなんて渇いていないのに「お茶が飲みたい。」と言った。その後、約二週間続いた入院生活で、私は何度となくナースコールを押しては、適当に頼みごとをした。 そして、ついに来た手術の日、手術室に入る直前、自分は死ぬのではとふいに思った。「嫌だ。」「怖い。」何度も言って、泣いた。多分、両親も泣いていた。手術室でマスクを付けられた所で、私の記憶は途絶えた。 次に目が覚めたのはICUだった。手術で切開された背中の筋肉が痛かった。涙が出た。看護師さんは「痛い?」と心配してくれたけど、私は自分が「生きている」という事実に泣いた。生死を分ける大手術を終えたような気分だった。難しい手術ではないと何度も聞いていたのに。今となっては少しおかしい。 私の背中には、今も大きな手術跡が残っている。その傷を見ると、あの時感じた「生きている」という気持ちが甦ってくる。そして、「生きたい」と強く思える。この先の人生で、つまずいたり立ち止まってしまった時、きっと私は背中の傷を見て、命を感じるのだろう。優秀賞
「生きる」
北村 彩乃さん(大阪府立八尾翠翔高等学校)
「生まれつき目と耳が不自由やから、一人で生きていくために資格を取って、それを活かして仕事してきたよ。」 二軒隣りに住む小さくてかわいいお婆ちゃんのこの言葉が、私の胸に強く響いた。なんて前向きで、すばらしい考え方なんだろうと感動し、尊敬した。 「限界」という文字がまったく似合わないたくましいお婆ちゃんは、80才を過ぎた今もいろいろなことに挑戦している。ある日、家に遊びに行くと、今までなかったパソコンに向かって、ちょこんと座るお婆ちゃんがいた。私はあまりにも驚き「見えるの?」と聞いてしまった。お婆ちゃんは、得意気に「見えてないよ。」と答えて、私の目の前でいくつかの点字の印がついているキーを組み合わせながら、ゆっくりと文字を入力し始めた。画面には、私の名前が入力されていて、嬉しくてたまらなかった。お婆ちゃんは、素敵な笑顔で私を見た。その笑顔を見ると、いつも自然と心の底から笑顔になれる。 テレビの音もラジオの音もない静かな部屋で、二人きりで過ごす時間は和やかで居心地がいい。そんなとき、お婆ちゃんはふと「命がある限り、いろいろなことを楽しみたい。」や「せっかく生かしてもらってるねんから、自分で納得のいく人生を送らんとな。」とつぶやくことがある。それを聞いて、お婆ちゃんは生きていくことについて、こんな風に考えているんだと知り、私も自分の人生について考えるようになった。卓球やゴルフなど、あらゆることに次から次と挑戦していくお婆ちゃんの姿には、生きる力強さを感じる。 人それぞれ、生き方はいろいろあるが時間を無駄にすることなく、楽しく生きるということは、とても大切だということを人生の大先輩であるお婆ちゃんに教えてもらった。いろんなことに挑戦し、そして楽しむお婆ちゃんに、私も負けてはいられない。命を無駄にすることなく、私は私の人生を精一杯生きていく。優秀賞
「失敗の中から学ぶこと」
佐藤 いづみさん(兵庫県立西宮香風高等学校)
今この社会は、忙しなく動き、私はそれを息苦しく感じるときがある。失敗してはいけないという空気が流れ、誰もが失敗を恐れる。失敗をするたびに厳しくなるルールは、自分も周りも苦しめていく。そんな社会の一番の被害者は、子どもたちだと私は思う。 私は高校に入ってから、保育所のボランティアや小中学生を対象とした野外活動のリーダーなど、様々な形で子どもたちと関わってきた。それらの活動の中で感じたのは、大人が子どもに手を出しすぎているということだ。子どもが経験をする前からたくさんのことを教え、子どもが失敗をする前から上手くいくように手を回す。それは一見、愛情あふれる優しさに見えるのかもしれない。でも、私はそんな環境にいる子どもたちが、大人の顔色をうかがい、大人から見える『いい子』でいるために自ら行動を制限しているように見えたのだ。 きっと、子どもと同じように大人も失敗が怖いのだと思う。だから子どもが失敗をする前に先回りしてしまう。でも、大人がそうやって先回りできるのは、自分の子どもの頃に同じような失敗を経験したからではないのだろうか?まだそんな経験の少ない子どもが、たくさんの失敗をするのは当たり前のことだと思う。大人だって、失敗を繰り返して大きくなってきたのだから。それなのに子どもに失敗をさせまいとすることは、子どもの学ぶ機会を大人が奪ってしまっているように感じるのだ。 何度失敗したっていい。失敗の中で子どもたちは学び、自分の力にしていくのだろう。そこに手を出すことなく最後まで子どもたちを見守り、失敗したことも全部子どもたちと一緒に受け止める。それこそが、本当の優しさであり、大人が子どもにしてやるべきことなのだと思う。私はそんな風に、本気で子どもたちと向き合うことのできる大人になりたい。優秀賞
「共に、闘う」
藤井 なり美さん(岡山県・金光学園高等学校)
「いのち」と言えば「使命・天命・宿命」これが我が家の三大キーワードだ。 私の父は私が4歳の時に亡くなり、祖父は母が14歳の時に亡くなった。母娘二代、父親を早く亡くした。私の父が亡くなってから、明るく楽天家の祖母、涙もろく気の強い母、そして、その二人からいつも「平常心を持つ人になれ」と育てられた私の三人の生活が始まった。 病気というのは、その人の気持ちや家族の思い、仕事の都合を全く無視して襲って来る。 私の父は肝臓がんだった。宮大工として修業し、建築技術者として道路や橋、病院、水族館等、多くの物を残して病に倒れた。私はまだ4歳だったが、父の作業着姿をはっきりと覚えている。 私の成長記録は写真で残されていて、いつも、そっくりな顔で父と私が写っている。 手術の3日前、外出許可を取り、サーカスに連れていってくれた。この日が父と撮った最後の写真だ。幼い私との、どんな小さな約束もきちんと守ってくれた父。何でもチャレンジするのが好きな父は、3度の手術を受け、短く忙しい人生を終えて天に帰って逝った。何でもできる父は、私のスーパーマンだった。その父が病気にだけは勝てなかった。病気が父の天命だったのだろうか。 父の闘病中から高校生になった今も、父と同じように病気と闘う人達の手助けになる医師になるという夢を、私は持ち続けている。 私の母は「人間は皆、使命を受けている」と言う。父は私に、誰よりも短い時間で、誰よりも命の尊さ、大切さを教えてくれた。 一生懸命生きることは、宿命に負けないこと。最期まで諦めないこと。例え、命期が見えたとしても、最期まで命を懸けて闘う患者と共に闘い続ける、宿命に負けない医師に、私はなりたい。優秀賞
「あの頃へ」
星野 葵さん(静岡県立気賀高等学校)
子ども時代の私たちは勇敢だった。自分の持つ知識の幅を広げることにためらいがなかった。その短い腕が届く限りの全てをつかみとり、すみずみまで調べた。自分一人でそのものを学び理解した。誰に教わることもなくツツジやサルビアの花の蜜の甘さを知った。光にかざすときらきらゆれる、大小様々なビー玉たちの美しさを学んだ。地面を調べ、初めて羽の付いたアリを見つけた時の驚きや感動の混ざった複雑な気持ちは、もうきっと味わえないのだろう。 今の私たちからは昔のような、ある種無謀とも言えるような凄まじい勢いがなくってきてしまっている。それは私たちに「一般的」な知恵がついてきたからだ。自分で調べ、自分で知り、自分で探し、自分から学ばなくとも、今では本やテレビなど多くの情報を理解し、自分の知識として吸収できるようになった。誰もが簡単に手に入れることのできる情報が増え、私たちの考え方、見方に「オリジナル性」がなくなってきた。 私たちは私たちの子どもの頃を思い出さなくてはいけない。あの頃の何も知らない私たちは勇敢であり無謀であった。だからこそ、思い出したくない失敗も多くあると思う。しかし、それらを全て受け入れ当時のスタイル、勢いを取り戻すことが今の私たちに最も必要な事だと思う。 身長が伸び、目線が変わり、様々なものが変わってきた今。今だからこそ見えてきたものを理解し、守るために。「子どもの考え」「大人の考え」そんな言葉に惑わされず、もう一度、自分の中にいる子どもを呼び起こす。 出会ってすぐに友だちになれたあの日を、周りも、自分も、全ての人々が笑っていたあの頃をもう一度取り戻すために。佳作
「大丈夫。」
井田 小和子さん(京都府立加悦谷高等学校)
「行きたくない」これが私の口癖でした。中学3年生にあがった頃から、私はクラスでいじめにあいました。学校に行くのが嫌で嫌で、毎朝学校の下駄箱が戦いの始まりでした。震える足を必死で我慢して、中に何も入ってないか確認してから、いつも上靴をはきました。「死ね」「消えろ」という言葉を何度も聞かされる日々は、私にとって地獄でした。ですが、一日の中で唯一私がほっと出来る時間がありました。それは自分の家、家族と過ごす時間でした。母は、私が心配をかけたくない一心で強がっている事にすぐ気づいてくれ、毎日話を聞いてくれました。それなのに私は、「生まれてきたくて生まれたんじゃない」と母にきつい言葉を言った事もありました。すると母は、「私はこの子を産みたい、この子じゃなきゃだめだと思ったから産んだの」と言ってくれ、それと同時に、自分自身も昔、いじめにあっていた事、でも今、こんな家庭が持てて幸せだという事を教えてくれました。父は、私に強くなってほしくて、母の様な優しい言葉はかけてくれませんでしたが、母に毎日私の様子をたずね、仕事帰りに私の好きなお菓子を買ってくれたりしました。私は、そんな不器用な父のさりげない優しさが嬉しくて、一人お風呂で泣いた事もありました。家族で食べる夕食は、学校給食の100倍、1000倍も、美味しいものでした。 そんな家族の支えで、中学を卒業した私は今、とても楽しい高校生活を送っています。私は、あの時、家族に相談できたから、今ここにいる事ができているのだと思います。だから今いじめられている子は、まず誰かに相談しよう。心配も、迷惑もたくさんかけたらいい。相談する事は逃げじゃなくて戦う事。死ぬ勇気があるなら、助けを求める勇気を持とう。私みたいに、誰かが絶対味方してくれるはず。それでも私は一人だと思う人がいるなら、伝えたい。大丈夫。私があなたの味方です。佳作
「今日より明日へ」
岡村 茜さん(高知県立岡豊高等学校)
「あの人よりはましだ」「私の方が上だ」「私の方が幸せだ」人は誰しも周りを見て、自分よりも劣っている部分を持つ他人を探し出し、心のどこかで安心している。 実際に私もテストなどで自分よりも点数の低い人を見つけると安心感を覚え、スポーツにおいても自分よりも足の遅い人がいるとほっとしている自分がいる。誰にでも覚えがあることだと思うが、それは非常に悲しい現実である。 以前、乙武洋匡さんの『五体不満足』という本を読んだことがある。私たちは「健康」な体で生活することができ、それを当たり前のことの様に思っている。私は体が「健康」ではない人たちのことを可哀想と同情の目で見ていたが、本人にとってはそれが「普通」なのである。本の中の「障害は不便です。だけど不幸ではありません。」という言葉は、今でも私の心の中にある。彼の前向きに生きている姿に、今まで自分が持っていた考えを恥ずかしいと思ったことを覚えている。 私は「健康」な体に生まれ、そのことについては不幸に思ったことはない。しかし、健やかな心を育んで生きてきたのかと自問した時、胸を張れないところもあった。 高校で出会った先生から「明日は今日よりも良い日にするために私たちは前向きでなければならない」という言葉を教えていただいた。仲間と励まし合い、自分を励まし、そうあり続けていきたいものだ。そういうことが幸せなのかもしれないと思うようになってきた。 私は将来、理学療法士となり、患者さんを「今日より明日へ」と励まし続けていこうと心に決めている。それができる理学療法士という仕事に、どんな職業よりも魅力を感じている。患者さんを支えながら一緒に「健康」へと近づけていきたい。 私は少しでも多くの人の不便を取り除くため、理学療法士になりたいと思った。佳作
「家の心」
川瀬 彩香さん(静岡県立気賀高等学校)
「ありがとう。」 誰もいない子供部屋に声を掛けた。返事は返ってこない。目を閉じれば、学習机が並び、ぐちゃぐちゃと沢山の荷物が置いてあった光景を思い出すことが出来る。しかし、今は荷物どころか、ゴミ一つ落ちていない。 「ごめんね。」 私がつけた『バカ』ってキズを指でなぞる。遊んでいる時についたのか?ケンカの時についたのか?キズが沢山あった。落書きが残っている壁もある。 「お休みなさい、だね。」 毎日、親子で布団を並べて寝た畳に寝転がってみる。おばけに見える染みがこっちを向いた、いつもの天井が見えた。 「ご飯、おいしかったよ。」 すっかり汚れた台所。もうご飯の匂いはしないけど、晩ご飯を作るお母さんの背中が目に浮かぶ。 「お風呂、楽しかったよ。」 頭を洗うことも、湯船につかることも、何でも遊びにして、笑いがあふれていたお風呂。昔と比べて、小さくなった湯船。 「片付けは完ペキだね。」 兄妹の遊び場だった居間。毎日怒られながら片付けたおもちゃたちは、ダンボールに詰められておとなしい。 「さようなら。」 私が過ごした11年間が詰まった家。玄関を出て眺めるとなんだかちょっと寂しそう。新しい家には、思い出しか連れて行ってあげられない。 家に話し掛けるなんて変な話だけれど、私の思いが伝わればいいと思った。大切に使われたモノに心が宿るらしい。だったらきっと伝わったよね! 「よろしくね。」 今日からココが私の家。玄関を入って、そう呟いた。佳作
「“ここ”が好き。」
児島 悠希さん(愛知県立桃陵高等学校)
「あそこのファストフード店、潰れるって。」 「ここのコンビニなくなったんだね。」 私の地元でよく聞く会話だ。過疎化が進んでいるんだと実感する。 そんな会話が繰り広げられている私の地元は、大きなデパートやビルは一つもない。最寄りの駅の近くには、海がある。そして私の家の前には川がある。その川の向こうには、一本道があるだけで、辺りは田んぼや畑が広がっている。通っていた中学校は、竹藪を越えたところにある。 高校生になって電車通学で都会へ出ることも多くなった。都会に住んでいる友達と話すと、聞いたこともなければ行ったこともない店の名前が、次々と飛んでくる。話についていけなくて、地元が嫌だと思ったこともある。自分の部屋から見える景色が、一面田んぼだと言うと、友達は驚く。それが嫌だった。でも、学校帰りの電車から見える地元の景色が、私はたまらなく好きだ。改札口を出て感じる都会とは違う雰囲気や空気、通りすがっていく人々の感じ。なんとも言えない安心感だ。やっぱり私は、“ここ”なんだ、と分かる。 過疎化が進んだって、友だちに驚かれたって、やっぱり私は私の地元が好き。春には菜の花が綺麗に咲いて、夏は青々とした稲が、まるで絨毯のように敷き詰められている。秋にはその絨毯が黄金色に変わる。そして冬は、花も葉もなく、感傷的な気分になる。そこがまた良い。 四季を感じることを、日本人なら忘れてはいけないと思う。忘れてはいけないというか、なんだか勿体ない気がする。そんなことを考えていると、都会に住んでいる人よりも幸せな気分になったりする。物よりも大切な何かを手に入れたような気がする。この自然は、ずっと守り続けたいと、心から思う。佳作
「『二人分』のいのち」
品川 菜穂子さん(大阪府立千里高等学校)
私にはお姉ちゃんが居る。でも私は一度も会ったことがない。その私のお姉ちゃんは、どうやら私が生まれる前に、母のお腹の中で亡くなってしまったらしい。このことは私が高校生になった時、初めて知らされた。 「菜穂にはお姉ちゃんが居るんだよ。」急にそう言いだした母に、私は「何言ってるの。私にはお兄ちゃんしか居ないよ。」とふざけて言おうとしたけれど、母の目を見て、口をつぐんだ。それくらい、母の目は真剣だった。 それからお姉ちゃんについて色々教えてもらった。お姉ちゃんは私より一歳年上だということ。名前は、まだ全然考えていなかったこと。初めての女の子なので、父と母はすごく喜んだこと。そして、もしお姉ちゃんが生まれていたら、私は生まれていなかったということ。 それを聞いて、私はとても複雑な気持ちになった。もしお姉ちゃんが生まれていたら私はこの世には居なかった。ということは、私はお姉ちゃんの「代わり」に生まれてきたのだ。もしかしたらお姉ちゃんの方が優しくて可愛くて、いい子だったかもしれない。私が「代わり」として生まれてきてよかったのだろうか。 そんなことばかり考えてしかめっ面をしていると、母は笑って言った。「菜穂のいいところと悪いところ、お姉ちゃんと『二人分』でできてるんだね。」その言葉に私は、「悪いところは全部お姉ちゃんのせいだね。」とふざけて言ったけれど、本当はすごく嬉しかった。 「代わり」ではなく「二人分」で私は生きている。欲を言えば、お姉ちゃんに会ってみたかったけれど、お姉ちゃんは私の中にいる。お姉ちゃんが分けてくれたいいところも悪いところも全部背負って、「二人分」のいのちの重さを感じて、私はお姉ちゃんの分も、頑張って幸せに生きていこうと思う。見ててね、お姉ちゃん。佳作
「今を生きる」
中島 優香さん(京都府立加悦谷高等学校)
胸に手のひらをそっとあててみる。確かに伝わる胸の鼓動。「トクン…トクン…」小さないのちは、今日も懸命に生きている。 今日、私は何をしただろう。汗をかきながら自転車を走らせ、行き交う人々に「おはようございます。」と、いつもの挨拶。教室の窓から体育の授業を見つつ、黒板の文字をノートに写す。節電と暑さ対策の一環として、校内で育てているゴーヤが枯れないように、友達と水をあげにいく昼休み。「また明日。」友達に笑って手を振って、自転車にまたがる帰り道。本当に何気ない一日。その何気ない一日が当たり前ではないと気付いた時、私はその日出会った全ての人や物たちに、幸せの一瞬をもらったと思える。 「高校どこ受けるん?」 叔母がそう聞いたのは、中学3年生の冬だった。「加悦高だよ。」「そうかぁ。頑張って勉強するんやで!」叔母は笑顔で応援してくれた。昔から何をするにも、叔母は無条件に私を応援してくれた。「おばちゃん、高校合格したよ。」と、絶対に伝えたいと思った。しかし、それは叶うことはなかった。叔母は天国へ旅立ってしまった。皮肉にも、叔母が亡くなったのは、高校入試当日の朝のことだった。ガンだった。叔母の病気のことは以前から知っていたが、死の一報を聞いた時、耳を疑った。信じたくなかった。入試を終えて、すぐ叔母の元へ向かった。眠るような叔母を目にしても、私はまだ叔母が生きているように思えた。しかし、棺に花と手紙を入れるいとこを見た時、叔母はもういないんだと、初めて思った。 胸に手のひらをそっとあててみる。生きていると感じる。叔母に見せたかった、この姿。「おばちゃん、学校楽しいよ。ちゃんと見てる?」佳作
「私のごちそう」
中村 奈央さん(京都府・京都橘高等学校)
保育園の帰り、祖母と手をつないで帰る。帰り道に真っ先に聞いていた話の内容を今でも覚えている。「おばあちゃん、今日のご飯なぁに。」 まだ高校生の私であるが、“お袋の味といえば何か”と聞かれたら、迷わず祖母のご飯全てだと答える。 両親が共働きのため、私が保育園に通っていた頃は祖母が迎えに来てくれ、そのまま祖母の家へ帰っていた。小学生、中学生になっても、帰る家はずっと祖母の家。祖母の家でご飯を食べ、両親の迎えを待つことが私の日常生活であった。 しかし、中学生の頃の私は、いわゆる思春期の真っ只中であり、「ダイエット中やしそんなご飯食べへん。」などといい、祖母のご飯を食べないときが多々あった。そのようなときの祖母の顔はとても寂しそうで、私が食べなかった分を片付けている姿はなんとも言えない気持ちにさせられた。 高校生になって、部活動で帰る時間が両親より遅くなったので、祖母の家には帰らないようになった。自宅に帰ると、母がご飯を作って待っていてくれる。祖母のご飯から離れ、初めて気がついた。どんなに祖母の味と離れることが寂しいことか。 十六歳になる、高校生になって初めての誕生日。母に「誕生日はおいしいご飯でも食べに行こう。何が食べたいか考えておいて。」と言われた。私は、すぐに答えた。「おばあちゃんのご飯がいい。」 私にとってのごちそうは祖母のご飯だ。どんな高級店にも負けない。そう気がついた今では祖母に必ず言う言葉がある。「おばあちゃんのご飯が一番だよ。」こんな簡単な言葉でごちそうを食べることができるなら、何度でも言おう。そして、言える“今”を大切にしたい。 ここまで健康に成長できたのも、祖母のご飯のおかげである。本当にありがとう、おばあちゃん。佳作
「掘りゴタツと家族」
西田 麗華さん(静岡県立気賀高等学校)
リビングにある掘りゴタツは、家族が集まる場所。しかし、家族全員が揃うことは、もう滅多にない。 私が小学生の頃は、掘りゴタツに両親と姉2人、兄、そして私の家族6人全員集まっていた。テレビをつけても、音が聞こえないくらいに騒がしい夕食が、当たり前だった。笑い声が絶えなくて、毎日楽しかった。中学生の頃には、掘りゴタツに両親、兄、そして私の家族4人が集まった。姉たちが一人暮らしをするために、家を出て行くことが、少し寂しかった。中学3年の始めには、父と兄、そして私の3人になった。会話がない。食事を同じ時間帯にしても、食べる物はバラバラだった。そして、食べ終わるとそれぞれの部屋で好きなことをしていた。あの時の私たちは、家族であって家族でない、ただの同居人だった様な気がする。高校生になると、掘りゴタツに父と私だけになった。兄も姉たち同様一人暮らしを始めた。狭かったリビングが、とても広く感じる。 盆になると、みんな遊びに来る。亡くなった母もその期間だけは、一緒にいるような気がした。掘りゴタツに足を入れて、最近あった出来事を話す。小学生の頃のように騒がしい夕食が始まる。テレビの音は、聞こえない。家族の笑い声が、家中に響いているからだ。私はこの家族といられる時間が好きだ。ツラいことを忘れさせてくれるくらいに楽しいからだ。盆が終わると、みんなそれぞれの生活に戻るため、帰って行った。静かになったリビングは、寂しい感じがした。しかし、そんな気分も忘れるぐらいに忙しい日々が始まる。 今年の夏も家族が集まるが、集まる人数が少し増える。姉が結婚したからだ。また騒がしい時間が始まる。私は、離れていても、家族は家族で変わらないと思う。何年経っても集まることが出来る家族をこれからも大切にしていきたい。佳作
「人の冷たさ。人の温かさ。」
横山 成美さん(三重県・鈴鹿高等学校)
クラスから「何でここにおるん?」そう笑いながら明らかに私のことを言っているような言葉が聞こえてきたのがきっかけだ。その後、クラスの子がひそひそ話すのを聞く度に私のことだと思ってしまい、怖くなった。学校では、誰かが人を嫌うとその嫌いな感情が伝染していく。少なくとも、私はそう思っていた。だからいつも人を恐れ、いつの間にか、クラスでの居場所がなかった。次々離れていく友達、それに家族とも上手くいかず、学校も家も苦痛だった。私は一時期、毎日死にたいと思っていた。だけど、死にたいと思っていても言葉にはできなかった。明日なんか来なかったらいいのに。なんで私っているんだろう。そう思っているうちに、日々眠れなくなり、食べられなくなり、自傷行為もするようになった。迷惑をかけては、自暴自棄になっての繰り返し。自分のことで精一杯で、周りの批判ばかり気にしていた。 だから見失っていたんだと思う。ずっと見捨てないで支えてくれた友達の存在を。そして辛さに耐えられなくなった私は、自傷行為のことを泣いて話した。そしたら、友達も一緒に泣いてずっと手を握ってくれた。「一人じゃないから。」「辛かったら受けとめるから。」と言ってくれた。更に涙が溢れた。私にはこんなにいい友達がいたんだ。今では普通に眠れて、食べられて、死にたいとも思わなくなった。 人の冷たさで人は傷つき、死にたくなることもある。しかし、人の温かさで人は立ち直り、生きていける。辛いことがあっても、私は人生がやり直せることを知っている。人生に何が正解で、何が不正解というのはわからない。だから、たとえ壁にぶつかったとしても、考え、悩み、行動していけばいい。それが生きるということだと思う。人は一人じゃない。周りの支えがある。今、どこかで苦しんでいる人も、明日を信じて、今を精一杯生きてほしい。