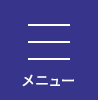入賞者発表
| 賞 |
テーマ |
タイトル |
受賞者 |
高校名/学年 |
| 最優秀賞 |
1 |
我が家を選んでくれて
ありがとう |
山村 亜梨沙 |
奈良県立香芝高等学校/3年 |
| 優秀賞 |
2 |
物と心 |
篭尾 知佳 |
高知県・土佐高等学校/3年 |
| 優秀賞 |
1 |
K君との出会いから |
笠原 愛 |
大阪府・関西福祉科学大学高等学校/3年 |
| 優秀賞 |
1 |
弟が残してくれたもの |
川元 瑛美奈 |
大阪府・追手門学院大手前高等学校/3年 |
| 優秀賞 |
3 |
ずっと続く思い |
浜道 しずか |
愛知県立桃陵高等学校/3年 |
| 佳作 |
1 |
生きていた証 |
亀谷 奈美 |
奈良県立桜井高等学校/3年 |
| 佳作 |
1 |
いのちの輝き |
河室 沙紀 |
三重県立津東高等学校/3年 |
| 佳作 |
1 |
私が「いのち」の輝きを
感じるとき |
高橋 円佳 |
大阪府・浪速高等学校/3年 |
| 佳作 |
3 |
まんまる家族のタコ焼きパーティー |
中尾 奈津希 |
大阪府立千里高等学校/3年 |
| 佳作 |
2 |
Y君との出会い |
道浦 舞野 |
大阪府立芦間高等学校/3年 |
(優秀賞・佳作は五十音順)
学校特別賞
三重県立伊勢高等学校
(応募点数が多く、1次・2次審査を通過した作品が多かった学校を選出しました)
テーマ
『いのち』
-
一人に一つしかないもの、それがいのち。いきいきと輝いたり、病気や事故で奪われたり、新しく生まれたり…あなたが感じたその重さやはかなさなど、「いのち」について自由に表現してください。
- 『子ども』
私の子ども時代、子どもといじめ、自分の未来の子どもに向けて、子どもの特権など、子どもにまつわるエッセイなら何でも構いません。近年の子どもを取り巻く状況についてのあなたの考えや、あなた自身の思い出など、自由に書いてください。
- 『衣・食・住』
身につけるもの、口にするもの、住むところ・・・身のまわりを見わたせば、あなただけのエピソードがきっとあるはず。思い出の服、わが家の食文化、お気に入りの風景など、あなたの衣・食・住にまつわる話を聞かせてください。
- 『自由テーマ』
「健康」または「教育」に関するエッセイならどんなテーマでも構いません。あなたの思いをエッセイに託してください。
過去の入賞発表を見る
応募要領を見る
最優秀賞
我が家を選んでくれてありがとう
山村 亜梨沙さん(奈良県立香芝高校3年)
「オギャー」と隣の分娩室から聞こえた。私は看護師さんに呼ばれ、母のもとへ。夏の暑い日の朝、私はお姉ちゃんになった。触ったらこわれそう。小さな体は、掌二つ分。吸う力がないためミルクが飲めず、なかなか体重が増えなかった。
退院して、二週間後のある夜、病院から家に電話があった。電話に出た母は泣いていた。「ダウン症」。生まれたばかりの弟の病名をそう告げられたのだ。二十一番目の染色体が一本多く、知的発達の遅れや心疾患などの合併症を伴う先天性の症候群だった。
最初、聞いた時は信じられなかった。しかし一歳七ヶ月で体重が七キロ。他と比べてはいけないとわかりつつも、我が子を思う母の心は不安だったにちがいない。でも、そんな不安や心配をさせないくらい、弟は成長した。
弟が四歳の時、祖父が亡くなった。ヨチヨチ歩きで遺体の前に行き、片言で「チューリップ」の歌を歌いだした弟は、小さいながらに死という事を分かっていたのか、目には涙がいっぱいだった。最後に孫から歌のプレゼントをもらって、天国へ行った祖父は幸せ者だ。
一つの命が消えた時、弟の行動は周りの人たちにとても心温まるものを与えてくれた。生まれた時こわれそうだったとは思えないほど大きく見えた。
素直に生きる弟へ。これから、困難な事がたくさんあるかもしれない。同世代と同じような「一人前」とは言われないかもしれない。あなたの思いをなかなか分かってもらえないかもしれない。でも、あなたは心で会話する子。ゆっくり時間をかけて分かってもらえばいいんだよ。ゆっくり成長する分、人生が十倍楽しめるから。
両親のあなたへの思いは人一倍大きい。あなたが心配で長生きするだろうね。あなたが生まれてきてくれたから、私はお姉ちゃんになれたよ。我が家を選んでくれてありがとう。
優秀賞
物と心
篭尾 知佳さん(高知県・土佐高校3年)
お金=自由度。現代社会では、物を手に入れ、したいことをするための自由度を決定してくれるのがお金だ、と考えられている。だが、「お金で買えないものはない」と思う一方で、私たちは常に満たされない心を抱き続けている。そして、新製品を次々と買っては満足を得ようとする。これには果てがない。いったい何が私たちの心を安堵させてくれるのだろう…。
最近よく目にする携帯用ゲーム機を片手に持ち歩く子どもたちの姿。テレビの画面には、持っていないと自分の子どもだけ仲間はずれになるという理由で、ゲーム機を買い与える母親像が浮かんでいた。大人は子どもへの愛情の注ぎ方を間違ってしまってはいないだろうか。
物を買い与えること、お金をあげること、これらも実際に愛情の一部だろう。だが、私の幼少時代を思い出してみても、この類の「ありがたみ」は瞬間にして消えることが多かった。それよりも、母に絵本を読んで聞かせてもらった記憶の方がはるかに強く残っている。気になることが出てくる度に「ねぇ」と話を中断させては疑問を投げかける私に、すぐに答えてくれることもあれば、笑ってごまかすこともしばしば。母はむしろ、そうやって娘と一緒に「道草」することを楽しんでいたのかもしれない。絵本の本筋から逸脱したところに、母子の会話が確かに存在していた。今となってはそのやりとりが、この上もなく幸せに感じられるのだ。
時の流れや物の発達は誰にも阻止できない。そのせいで、人の心まで変わってしまおうとしている。気がつけば私も、手に取りたいと思うもの、美しいと思うもののほぼ全てが「物」であり、その追求に明け暮れていた。
物は愛や優しさの尺度にはなれない。物に価値を置く現代に、まず見直さなければならないのは、親と子のコミュニケーションだ。目には見えないが、胸の奥底にしみ込んでいる愛情こそ、心が休まるものなのである。
優秀賞
K君との出会いから
笠原 愛さん(大阪府・関西福祉科学大学高校3年)
今、この世の中に「命」を意識し、実感しながら生活している人はどれだけいるのでしょうか。私はある一つの出会いから、決してあたり前ではない「命」の存在を知りました。
小学校四年生の春、引っ越し先の京都で初めて、K君とその家族に出会いました。K君は、生まれつき運動機能障害を持つ四歳の男の子でした。つたい歩きを始めた当時一歳の私の妹より三つ上でしたが、首さえすわっていませんでした。K君の母親は、気さくで明るく私たちにK君の障害のリスクや、リハビリセンターでの話をよく笑顔で話してくれました。しかし当時の私には、その笑顔の重さを知るほどの知恵も経験もありませんでした。
中学二年生の時、既にK君との出会いから私の未来は理学療法士という道へ向いていました。そんな時に母から聞いた言葉は、心に重く響きました。「K君の障害が発覚した時、K君のお母さんは『Kと一緒に死のう』って思ったんやって。」死を思うほどの絶望があったことなど、あの笑顔からは想像もつきませんでした。死を思いとどまらせたのは、他の二人の子どもたちの存在だったそうです。K君への愛情は、家族のみんなに反映しているようでした。私がK君を思い出す時、笑顔ばかりが浮かんできます。言語障害もあったため、彼は言葉で表現できませんが、確かにK君は幸福の中で生きていました。その笑顔がそれを物語っていました。
今K君は、リハビリをしても無駄であることを遠回しに言われているようです。しかしもちろん家族の誰もがあきらめていません。特に母親は、「Kは絶対に歩く」と力強く私たちに話されます。
様々な個性が存在するだけ、支え合う世界があるだけ。そこに障害という壁は存在しません。障害という個性を知り、受け入れ、誰もが輝ける広い視野を持った世の中に塗り替えていこうと私は決心しています。
優秀賞
弟が残してくれたもの
川元 瑛美奈さん(大阪府・追手門学院大手前高校3年)
「本当は、もう一人家族がいたんだよ。」
そんな衝撃的な告白を受けたのは、今年になってからのことでした。母は涙ながらに真実を語ってくれました。
弟が母のお腹の中にいたのは六ヶ月間でした。そのころ私は二歳で、母と父の離婚が決まり、父は母に弟を産まないでほしいという意思を伝えました。当時の母には職も財力もありませんでした。そのような状況で、私と弟を一人で育てていけるのだろうか、という不安があり、悩み続けた結果弟との別れを決意したのだということでした。
思いもよらぬ突然の事実に、私は言葉を返すことができませんでした。普段はいつも笑顔でたくましい母だけに、その頬をつたう涙は私の胸を締めつけました。「せっかく授かった大切ないのちだったから、本当は産んであげたかったんだよ。でも当時の状況ではどうすることもできなかった…。弱いお母さんでごめんね…。」そう言って母は、私をぎゅっとだきしめました。母の腕から、今までの苦悩や心の痛みが伝わってくるようでした。きっとたくさん悩み、何度も産もうと考えたのだと思います。まだ産まれていなくても、確かに母のお腹の中にいて、生きていたのですから。だからこそ、別れの決断は本当につらいものだったでしょう。しかし、弟は母に大切なものを残しました。いのちの重さです。弟のいのちは一つだけでした。一度失われたいのちは、もう戻ってくることはできません。代わりもいません。だから尊く、はかないものなのだと思います。そのことを弟が伝えてくれたと思います。なぜ母が看護師の道を決意したのか、やっと分かったような気がしました。
当時の私がもう少し自分の意思を伝えられる年齢であったならば、母を安心させ弟を救えたかもしれないと思うと、もどかしい気持ちになります。弟が過ごせなかった人生を、弟の分まで大切に生きていこうと思います。
優秀賞
ずっと続く思い
浜道 しずかさん(愛知県立桃陵高校3年)
暑さが厳しくなり、衣替えをする時、私は必ず浴衣を二枚出す。一枚は、今年自分が着るもの。そしてもう一枚は、私が小学生の頃に着た紺色の浴衣とオレンジ色の帯だ。もう着られない浴衣を出す必要はないのだが、毎年毎年、どうしても見たくなって出してしまう。きっとこれが、私と母、そして祖母をつなぐ、大切なものだからなのだろう。
小学生の頃の私は、浴衣にすごく憧れていた。夏祭りの時に見る色とりどりの浴衣がとても綺麗で、印象的だったからだと思う。毎年母に、浴衣が欲しいと言っていたのだが、返ってくる返事はいつも決まっていた。「まだ早いでしょ。」毎年夏祭りぎりぎりまで粘るのだが、いつも私の負け。仕方なくいつもどおりの服装で夏祭りに出かけていた。
それは小学五年生の夏のことだった。ある日母が私を呼び、箪笥から何かを出してきた。何だろうと不思議に思いながらそちらへ行くと、そこには紺色の浴衣が置いてあった。母が若い頃に着ていたものらしく、今の私だと丁度良い丈だということで、出してくれたそうだ。帯はだめになってしまった為、祖母が作ってくれたと教えてもらった。母はどうしてもこの浴衣を私に着て欲しかったので、今まで新しいものを買わなかったと話してくれた。丈を確認するために袖を通した私は、浴衣を着ることよりも、その母と祖母の思いがとても嬉しかった。
母の思い出、祖母の思い、そして私の思い出が詰まっているこの浴衣と帯は、私にとってとても大切な宝物だと思っている。そんな宝物を、今度は私の妹にあげようと私は考えている。私が感じた嬉しさ、温かさを、今度は妹に感じてほしいと思うからだ。そうやってずっとずっと、この浴衣がつながっていけばいいと願っている。
時が過ぎても、必ずあなたの周りには誰かの気持ちが、心がある。そんなことを感じてほしいと思うから。
佳作
生きていた証
亀谷 奈美さん(奈良県立桜井高校3年)
人は人を失ってから、その人がどれだけ大切な人だったかを気づかされる。しかし、失った人は帰ってこない。大切な人が帰ってくることは決してないのだ。
私の祖父が亡くなったのは冬の寒い日の夜。それは突然の死だった。私の心は横たわる祖父の顔を見ても、冷たい頬に触れても、祖父の死を拒んでいた。いつも居間の扉を開ければ「おかえり」と迎えてくれた。しかし、もう扉を開けても「おかえり」という人がいなくなった居間と私の心には違和感があった。
告別式も終わり、祖父が写真だけになった時、初めて祖父の死を受け入れることになった。そして、祖父の死は現実なんだと、少しずつ祖父の死と向き合うようになった。祖父の死と向き合う度に、私の目からは涙がこぼれる。もう二度と祖父とは話し合うことも、笑い合うこともできない。私の目からこぼれる涙には、寂しさと悔しさが混じっている。けれども、私の目が涙をこぼす度、祖父を思い出す度に、もう一つのことを再確認する。それは、祖父は確かにいたということだ。一緒に過ごした日々が夢ではないのだと。居間の扉をあけ「おかえり」と私を迎えてくれていたのは、確かに祖父であったと確かめることができるのだ。
もう一度祖父に会うことはできないけれど、私には祖父との思い出がある。それは、決して多いとは言えないけれど、私の大切な宝物の一つである。
今、私にできることは、祖父との思い出を忘れずに精一杯生きることだ。それが、祖父が生きていた証になると思うのだ。祖父の死を通し、死の重さを、生きることの大切さを知った。命は儚く、もろいものだと知った。命は一人に一つずつ分け与えられたものであり、それは決して平等なものとは言えないけれど、精一杯生き、生きているということに感謝しなくてはならない。だから私は笑顔で今日を迎え、一日一日を精一杯生きていく。
佳作
いのちの輝き
河室 沙紀さん(三重県立津東高校3年)
「いのち」とは何だろう。「死ぬ」とはどういうことだろうか。私が初めて強く「いのち」の重さを感じたのは、まだ少し厳しい暑さが残っていた昨年の8月末、大好きな祖父の亡くなった夜であった。私たちは病室で、祖父を囲んでいた。前々から何度かもうだめだと言われていたが、今回は本当にだめらしかった。
医師から「あと数時間です。」と言われたが、私には実感がわかず、一生懸命祖父に話しかけていた。祖父はもうほとんど意識を失っていたが、私の声に時々反応した。
真夜中を過ぎた頃、祖父は眠るように天国へ旅立っていった。1秒前までは生きていたのに、おじいちゃんはもう死んだの?私には生死の境目が分からなかった。最後に、家族みんなで祖父の顔を拭いていた時、祖父はまばたきをしたような気がして、私はハッとした。
お葬式が済んで、祖父を焼いた。大好きだった祖父が灰になった。人間は高熱で焼かれると、こんな形になるのだと、私は驚いた。
私は今でも家のどこかに祖父がいるような気がする。祖父は今でも私の胸の中では生きている。
「生きる」ということは、人と人とのつながりを大切にすることだと、私は祖父の死から学んだ。その人がどのように生きたかということが、死ぬ時に示されるのではないだろうか。そして、人と人とのつながりや友情、愛が新しい「いのち」を帯びて、また連鎖していく。私もいつか結婚して子どもが生まれたら、その事を伝えていきたい。
「いのち」が輝くということは、必ずしも名誉や富の問題ではない。苦労して家庭を築き、家族に感謝されて生きた人、社会の片隅で人のために尽くした人など、いずれもすばらしい「いのち」の輝きである。私もそういう「いのちの輝き」を大切にしていきたい。
佳作
私が『いのち』の輝きを感じるとき
高橋 円佳さん(大阪府・浪速高校3年)
私の祖父は、約25年前に脳梗塞で倒れ、介護を要する状態になってしまいました。食事・排泄・入浴、全てにおいて、祖母の介護を受けています。言語に関しても、全く話すことも、欲求を訴えることもできない状態にあります。祖母は毎日、排泄の世話をし、食事は祖父の食べやすいようにミキサーにかけ、スプーンで一口ずつ口に運んでいます。服を着替える時も、体を拭いたりしています。高齢社会において、今ではどこにでもあるような光景ですが、祖母はほとんど反応のない祖父のために、毎日毎日介護をしています。ある日、母と買い物に行った時、祖父の好きなプリンを買って帰りました。それを私が祖父に食べさせますが、大きな反応はありません。しかし祖母は、私のその姿を見てとても喜んでくれ、祖父に代わって感謝の言葉をかけてくれます。生活する様子を見ていると、ベッドに横になることしかできない祖父は、何を楽しみに、何を考え、何を思っているのだろうと、ふと考えることがあります。いのちある限り、この状態は続きます。
生命はその人の寿命であり、心臓や脳の機能が活動し、生物として存在するものだと言われています。しかし、祖母の介護を受ける祖父の場合、単なる一つの生命ではなく「いのち」を感じるのです。祖父母を通して思うのは、いのちはもちろん祖父のものではありますが、祖母のものでもあるように思えます。祖父のいのちは、祖母の生きる原動力になっているからです。
「いのち」は、周囲の人々に影響を与えるものだと思います。それは、人に対する思いやりや優しさです。また、いのちはその人ひとりだけのものではなく、関わる人の中に深く根付き、存在していくのだと感じています。時々、祖父母の傍にいると「いのち」の輝きを感じることがあります。久しぶりに祖父母の喜ぶ顔が見たいので、大好きなプリンを買いに行こうと思います。
佳作
まんまる家族のタコ焼きパーティー
中尾 奈津希さん(大阪府立千里高校3年)
私の家族は忙しい。父は毎晩遅くまで仕事、母はパート、大学生の姉もアルバイトで帰りが遅い。また、妹と私は受験をひかえているので塾や予備校で家にいないことが多い。そのため家族みんなで食事をすることが、最近ではめっきり少なくなってしまった。
しかし、どんなに忙しくても私たちが集まる日がある。それは半年に一回我が家で開催される、タコ焼きパーティーの日だ。この日は必ず全員が集まる。まず一番オーソドックスなタコ焼きから作り始める。十年以上続いているこの行事に父は一種のプライドを持っており、普段全く料理をしない父が、この日だけは粉の配分からなにから全て自分でやる。私たち子どもはタコ焼きをひっくり返すのが仕事で、普段食事を作ってくれる母と祖母は何もしなくてよい。十年以上作り続けたタコ焼きは年々おいしくなった。初めはベチャベチャしていたタコ焼きもだんだんふわふわに、そして父はこの二、三年で「外はカリカリ中はトロトロ」を習得した。他にもチーズやツナ、コーンに梅干しなど毎年いろいろな味付けを開発する。新しい味付けを思いついては皆で試し、「おいしい」「まずい」などと言って大騒ぎするのも一つの楽しみだ。そして最後にデザートとしてホットケーキミックスをタコ焼き器に流し入れてベビーカステラを作る。それを食べてタコ焼きパーティーは終了する。食べた後の片付けも全員でするのがこのパーティーのルールだ。
大阪といえばタコ焼きというイメージがあるが、私にとってタコ焼きは、大阪のシンボルとしての食べ物というだけではない。タコ焼きは、生活軸のバラバラな家族を集め、その見た目のとおり家族を「一丸」にしてくれる食べ物だ。
佳作
Y君との出会い
道浦 舞野さん(大阪府立芦間高校3年)
高校三年生となる春、ボランティア活動を始めた。障害を持つ子どもをサポートし、共にさまざまな活動をするというものだった。初めて経験すること。初日は、とても緊張しながら、施設へ向かったことを覚えている。
そして、Y君と出会った。小学三年生の元気な男の子。一言目を、少し戸惑いながら話しかけたのは私の方だった。しかし、反応はそっけなかった。初めて見る私に、Y君も戸惑っているように見えた。それでも、Y君のことを知りたくて、たくさん話しかけた。その日は、Y君の好物を知ることができた。
二日目、Y君も少し慣れてくれたのか、よく話しかけてくれるようになった。そして、この日はミニ運動会をした。二人で大きなズボンをはき、手をつないで、まと当てやボーリングをした。Y君は楽しそうに笑っていた。私も笑った。一瞬、Y君との距離が縮まった。そう思うことができた。
施設の春休み最後の日、遊園地へ行った。二人で観覧車に乗った。Y君は嬉しそうにずっと外を眺めていた。急流すべりでは、怖かったのか、顔がひきつっていた。そんな姿も可愛かった。やがて、ボランティア活動の、あの心を膨らませた日々が、終わってしまった。
初めて会った時から思い返してみると、戸惑った顔のY君。よく話しかけてくれたY君。笑顔を頻繁に私へ向けてくれるようになったY君。それらの表情すべてが、私を慕ってくれているように思われた。障害を持つ子への考え方も変わった。誰でも個性があり、意思を持ち、行動している。何の変わりもないのだ。
さて、この夏、また施設でのボランティア活動が始まる。子どもたちと私自身、共に過ごす中で、次はどのように成長することができるのか。そして、どれだけ多くの笑顔を見ることができるのか。私の心は、自然と弾んでいる。