2022.12.01
看護実践研究センター第8回研修会「医療的ケア児と家族が安心して暮らせる地域づくり」を開催しました。
看護実践研究センター地域包括ケア部門では、乳幼児から高齢者までの看護分野における連携および他職種との連携と協働からのケアシステムおよびケアのあり方を探求するとともに、それらに関連する情報を提供し、健康増進に寄与することを目的としています。
医療の発達とともに在宅で医療的ケアを必要とする重度心身障害児は増加しており、その生活を維持するには、医療機関における看護から在宅看護への継続看護が重要であり、さらに公的支援機関である保健所・福祉部門、そして教育機関等との連携が必要です。
そこで、本研修会では、令和4年11月26日(土)に、「医療的ケア児と家族が安心して暮らせる地域づくり」をテーマとして、大阪発達総合療育センター医療コーディネート事業室(同センター元訪問看護ステーションめぐみ所長)絹川美鈴様を講師としてお招きし、開催しました。
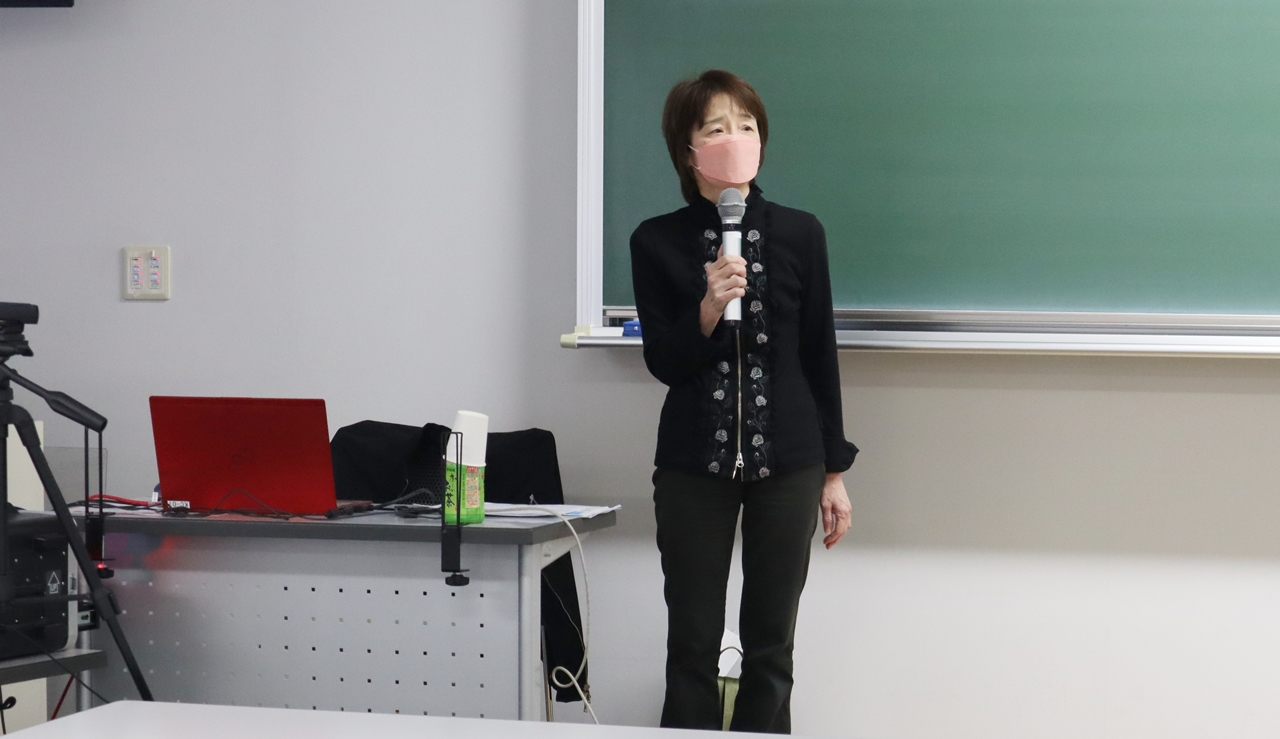
コロナ禍が継続している状況ですので、畿央大学での対面参加とオンライン参加のハイブリット開催とし、保健センター、保健所、医療、福祉、教育機関の保健師、看護師、保育士、教師といった様々な職種の43名の方にご参加いただきました。オンライン参加では九州、名古屋、京都など県外からの参加もありました。
講師からは、医療的ケア児に対する医療機関から在宅生活への移行支援、在宅生活を継続するための家族への支援とその継続に不可欠な地域包括ケアシステム活動を展開している支援機関(人材含む)との連携と協働の実際について、支援されたケースの状況を含め、分かりやすく作成されたPowerPoint資料を基にお話しいただきました。

在宅生活を継続させるための4つの視点である、地域支援、家族支援、移行支援と医ケア児が小児であることで重要となる発達支援や就学支援について、実践報告の中で現実として生じる課題を示していただきました。

質疑応答では、「保健師との連携で感じていること」、「家族の気持ちを捉えるコツ」「ちょうどいい距離感の取り方」など具体的な質問が多くありましたが、時間を延長してご丁寧に回答をしていただきました。このご講演を拝聴して、医療的ケア児の養育者の頑張りを認め、励ますだけでなく不安なことを表出できるように声かけを行い、共通の支援目標に向かってチームで話し合いながら情報共有し連携して支援を行うことが重要であると感じました。

参加者の方からは、「医療的ケア児への関わりで、傾聴や寄り添いの大切さを改めて考えることができた」「医療的なケアだけでなく、その人の生活にも目を向けて支援していきたい」というお声をいただき、対象者やその家族の思いに寄り添う支援について考える貴重な機会となりました。
看護実践研究センター地域包括ケア部門
看護医療学科 准教授 田中 陽子
【関連記事】
第4回看護医療学科卒後教育研修会「看護における臨床判断」を開催しました。
6/26(日)第1回 エコマミ公開講座で看護医療学科 山崎教授が講演を担当します。 2/1(火)「高齢者住まい看取り研修会」のご案内~畿央大学看護実践研究センター
2/21(月)「発達障害の一人称体験オンライン研修会」のご案内~畿央大学看護実践研究センター
第3回卒後教育研修会「コロナ禍の看護の現状~やさしさをチカラに変える 現場の声から~」を開催しました。
よく読まれている記事
カテゴリ
タグ
キーワード検索
アーカイブ












