2025.11.18
地域リハビリテーション研究室大学院生・研究員の学会での活躍をご紹介~健康科学研究科
地域リハビリテーション研究室大学院生・研究員が第84回日本公衆衛生学会総会、第12回日本予防理学療法学会学術大会で発表を行いました。その内容をご紹介します。
第84回 日本公衆衛生学会総会
2025年10月28日(火)~31日(金)の4日間にかけて第84回 日本公衆衛生学会総会がグランシップ(静岡県コンベンションアーツセンター)で開催されました。今年のテーマは「フェーズフリーの地域づくりと健康危機管理」でした。フェーズフリーとは、平時の物や仕組みが、危機時にも垣根無く役立つことです。日本公衆衛生学会は、80年以上の歴史を持つ学会であり、その領域は母子保健から栄養関係、中高年の健康増進、高齢者福祉と非常に幅広く、著名な専門家の方々が多数参加されています。また地域包括ケアシステムや介護予防関連の演題も非常に多く、リハビリテーション専門職の参加、発表も増えてきていることから、地域理学療法や予防理学療法との親和性も高い学会であると言えます。
地域リハビリテーション研究室からは、修士課程2年の田中 明美氏(奈良県福祉保険部)が修士研究のデータを活用した口述発表を行いました。

田中 明美 (修士課程2回生)
演題名:「短期集中型予防サービスの長期的効果の検証」
フレイル※1は可逆性(もとの状態に戻せる性質)であることを包含した概念であることから、これを立証する事業として短期集中型予防サービスの効果が注目されています。これは要支援者を対象に、リハビリ専門職等を活用しながら短期間で集中的な支援を提供し、生活機能の改善や維持を図るサービスとなります。
これまで短期集中型介護予防サービス前後の短期的な効果は数多く報告されていますが、要介護発生率の抑制効果や予防給付サービスを受けている要支援対象者との費用対効果を10年間にわたり検証したものは存在しません。本研究の結果ではサービス利用群は対照群に比較して新規要介護発生リスクが有意に低いこと(部分ハザード比=0.52,95%信頼区間:0.33–0.80,p<0.01)、各参加における観察期間中の総給付額/追跡月数は、サービス利用群が42,655円/人に対し、対照群で85,770円/人と有意に少ないことを明らかにしました(p=0.03)。
※1 フレイル…加齢によって心身が衰え、健康と要介護の中間にある状態。

畿央大学 健康科学部理学療法学科
畿央大学大学院 健康科学研究科
地域リハビリテーション研究室
教授 高取克彦
第12回日本予防理学療法学会学術大会
2025年11月8日(土)~9(日)の2日間にかけて第12回日本予防理学療法学会学術大会が令和健康科学大学(福岡県)で開催されました。今年のテーマは「あらゆる年齢のヒトが健康的な生活を維持するための疾病・障がい予防の探求」でした。予防理学療法学会では、学校保健や障がい者スポーツ、フレイル・介護予防、ヘルスプロモーションと幅広く、地域に包括的に健康増進や疾病・障がい予防を推進するためには分野横断的に学ぶ機会となる学会であります。また、本学会では介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中C型サービスの取り組みや財政効果、介護予防施策の課題についての発表もあり、今後の行政の立場としての介護予防事業の展開に大変参考になりました。
地域リハビリテーション研究室からは、修士課程修了生の中北 智士氏(客員研究員・貴志川リハビリテーション病院・紀の川市役所)が口述発表を致しました。

中北 智士(客員研究員・貴志川リハビリテーション病院・紀の川市役所)
演題名:「フレイル高齢者の新規要介護発生率が低い地域の特徴は?2年間の追跡調査」
フレイルとは、健康と要介護状態の間の状態と位置付けられ、要介護リスクが高いことが報告され、より早期からの介入が重要とされています。また、フレイル有病率や要介護発生率には地域内格差の存在が指摘されているものの、フレイル高齢者の介護予防に資する地域特性は十分に明らかとなっていません。
そこで、本研究では、地域在住の前期高齢者のフレイル・要介護発生率の地域内格差の実態を調査し、フレイルであっても要介護認定を受けにくい地域の特徴を検証しました。地域在住の要介護認定を受けていない前期高齢者8,911名を研究対象とし、フレイル有病率や要介護発生率を合併前の旧町5地区で比較検討しました。本研究では、フレイル有病率は11.0%~16.1%(P=0.022)と地域内格差を認めましたが、要介護発生率には有意差を認めず(P=0.761)、フレイル有病率が最も多いものの新規要介護発生率が低い地区では、フレイル高齢者の自治会やサロン・老人会などの地縁活動への参加率が他の地区よりも多い結果でした(P=0.034)。当地区では従来から地縁活動が活発であり、このような社会文化的要因によりフレイル高齢者の地縁活動への参加が促進され、介護予防に寄与している可能性を示唆しました。人口減少が進む地域において、このような地域コミュニティのさらなる醸成が重要であると考えています。
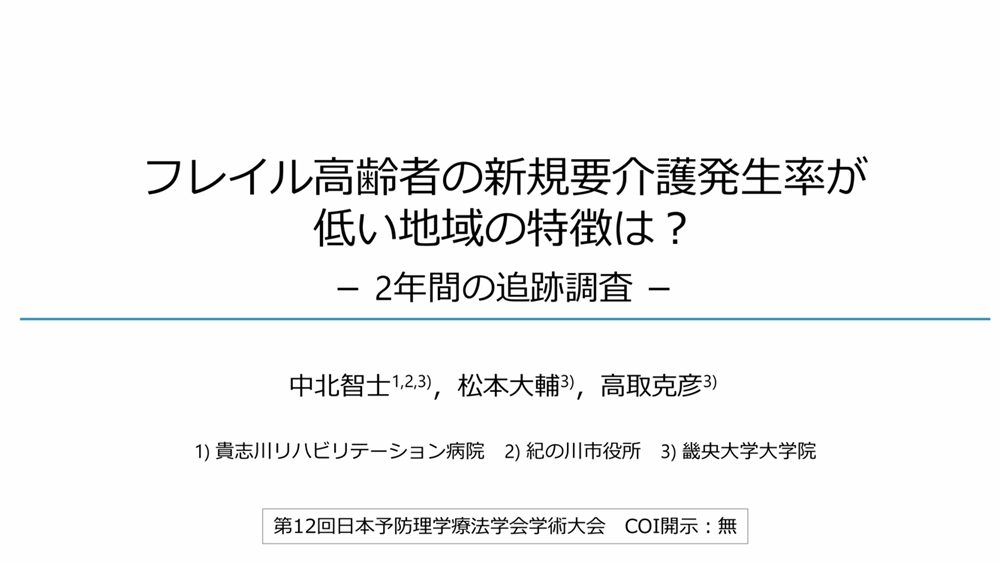
客員研究員として地域リハビリテーション研究室に所属することで、多角的な視点をもってデータ分析・解釈が可能となり、行政や地域社会にとって有益な報告ができると考えています。また、このような学会に参加することで、他市町村で活躍されている先生方と情報交換することができ、より幅広い視点を持って日々の業務にあたることが可能になると感じています。
最後になりますが、地域住民および行政職員の皆様には、本研究の実施を快く承諾していただき、深く感謝申し上げます。
畿央大学大学院 健康科学研究科
地域リハビリテーション研究室
客員研究員 中北智士
関連記事
第23回日本神経理学療法学会学術大会にて本学関係者が多数登壇・受賞しました!
第35回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会で2年連続となる「医療の質特別賞」を受賞! ~ 健康科学研究科
フランス・リヨン神経科学研究センターのHugo ARDAILLON 氏が畿央大学を訪問されました!~ ニューロリハビリテーション研究センター
第15回呼吸・循環リハビリテーション研究大会を開催しました!~健康科学研究科 田平研究室
よく読まれている記事
カテゴリ
タグ
キーワード検索
アーカイブ












